この記事をおすすめする人
① 学級崩壊経験者
② 叱ることに抵抗を感じている人。
③ 子どもたちのステップアップを望んでいる人。
「けてぶれ」「自由進度学習」「個別最適化」など、チャレンジしたけど、放任主義的な感じになって、うまくいかなかった人って、案外少なくないと思います。
私はその一人です。←その時、一緒に組んでいたベテラン教諭は、私に向かって「けーわい先生の学級は崩壊しているよ!!」って、言われました。(その時の悔しさが、今の原動力になっているのは、このブログ上での話)
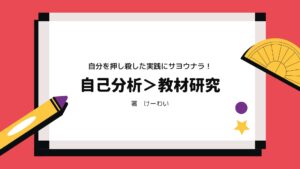
https://item.rakuten.co.jp/bookfan/bk-4313653775
https://books.rakuten.co.jp/rb/16596578/?variantId=16596578
そもそも、最初から自分の頭で考えて頑張れる人なんて、ほとんど居ないと思います。
「自分の頭で考えて頑張れる人」になるには、ある程度トレーニングが必要だと思います。
そうでなければ、「ライザップ」などの、パーソナルトレーニングが流行るわけがありません。
強い意志で最初からダイエットができないのと同じことです。
https://books.rakuten.co.jp/rb/14394692/?l-id=search-c-item-text-01
ライザップのパーソナルトレーナーのように、まずやり方を教え、進捗管理を徹底すれば、9割の子どもは、「自分の頭で考えて頑張れる」ようになると思います。
ちなみに、イチロー氏も、「今の若い子は酷」と嘆いておられます。
https://www.sponichi.co.jp/baseball/news/2023/11/06/kiji/20231106s00001002555000c.html
教師が意識できる取り組みは以下の3つが考えられます。
① やり方を示す。
昨年度は、私は小学二年生の担任だったので、発達段階的に宿題はこちらで決めていました。ただ、漢字ドリルは自由に進めていいことにしていたので、ドリルを自由進度にしていました。
② 進捗を管理する。
→私は声掛けだけでなく。進捗表を教室に貼って、終わったところにチェックできるようにして、子どもたちが自分で進捗度を確認できるようにしました。
③ 締め切りを明示する。
いつまでにどこまでやればいいのか明示しておくことです。
https://books.rakuten.co.jp/rb/14394692/?l-id=search-c-item-text-01
これは、結構忘れがちだったり、言いっ放しになったりしまって、グダグダになってしまうことも珍しくありません。ここが最もうまくいかないところだと思います。
締切は、言うだけでなく、教室に掲示して見える化し、適宜、声をかけていくことをオススメします。
また、先の進捗表を用いて、遅れている子どもには個別で声をかけ、「いつまでにやるのか」や「困っていることはないか」など、声をかけていくと良いと思います。
正直、それでも「課題を終えられない子ども」はいますが、遅れを取り戻せるように、声をかけ続けていくほかないとないと思います。
勿論、行き過ぎた声掛けは、「不登校」や「体罰」の原因となるので、配慮は必要ですが、ある程度、独り立ちするまでは、子どもたちのパーソナルトレーナーとして、伴走していくべきでしょう。
これを怠ると、ほとんど子が落ちていき、学級崩壊の一因となる可能性があります。
ただ、現在は特別支援学級知的クラスの担任なので、「自分で考えて頑張る」ということに大きなハードル感じざるを得ず、「先生の指示を聞いて頑張る子ども」にさせてしまっている感が否めません。
知的の子どもにも自主性を育むことができる、良い取り組みを知っている方がいればご教授ください。

