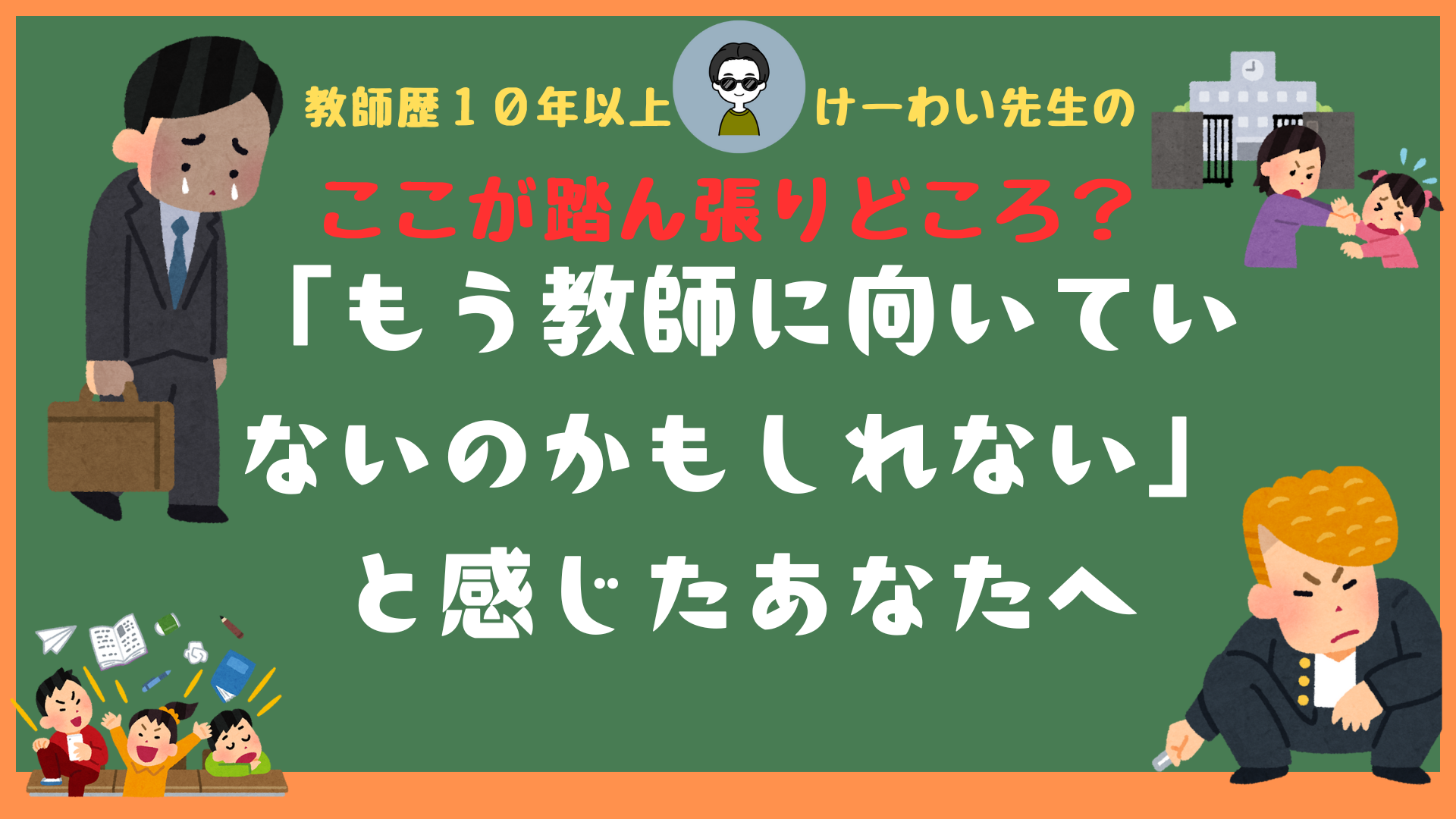けーわい
けーわい子どもたちとの関係ではなく、周囲の大人たちとの関係に悩み、教師としての自信を失いかけたことはありませんか?
一番苦しかったのは、「誰からも信頼されていない」と感じた瞬間でした。
子どもたちとの関係以前に、大人社会の中で孤立していく感覚は、想像以上に心を削りました。
この記事では、私自身が経験した学級崩壊と、その中で見つけた「本当に大切なこと」についてお伝えします。同じように悩んでいるあなたの参考になれば幸いです。
学級崩壊の経験から見つけた、本当に大切なこと
「どうしてこんなことになったのか」「私の何がいけなかったのか」
そんな問いが頭の中をぐるぐると巡り、気がつけば自分自身を責めてばかりいました。
でも、あの経験があったからこそ、私は「教師であることの意味」を深く考えるようになったのです。
この記事では、学級崩壊を通して私が見つけた、本当に大切なことについて綴ります。
今、苦しんでいる先生、迷っている先生にとって、何かひとつでも心に届くものがあれば──そう願っています。
左遷、孤立、そしてコロナ禍
コロナ禍の前、校長との教育方針の違いから左遷され、新たな赴任先では厳しい目と不遇な扱いが待っていました。さらに、コロナ禍によって体験活動は制限され、毎日のように校長室へ呼び出され、周囲の先生たちからも様々な指摘を受ける日々が続きました。
「出る杭は打たれる」という空気の中で、心は次第にすり減っていきました。
学級崩壊、そして孤独
その末に訪れたのが、学級崩壊でした。
何をしても届かない、何をしても認められない――そんな深い孤独の中で、私は立ち止まらざるを得ませんでした。
でもあのとき私は、自分自身に問いかけ続けました。
「それでも、教師を続ける意味はあるのか?」と。
この記事では、あの経験の中で私が見つけた「本当に大切なこと」について綴っています。
今、同じように苦しんでいるあなたへ。ほんの少しでも、前を向くきっかけになりますように。
学級崩壊を経験したとき、何が一番辛かったか
信頼を失ったと感じた瞬間
一番苦しかったのは、「職員の誰からも信頼されていない」と感じた瞬間でした。子どもたちとの関係以前に、大人社会の中で孤立していく感覚は、想像以上に心を削りました。
新任校の初日、校長との個別面談は1時間に及び、重苦しい空気の中で「あなたには問題がある」と言われているような時間でした。その印象は、その後の毎日に尾を引きました。
授業中、後ろからあれこれと口を挟む同僚。子どもへの声かけよりも、私の指導を上から修正するような態度。
極めつけは、ある日。書写の先生に悪態をついた子どもに対し、教頭・教務主任・校務主任が、私を差し置いて勝手に指導を始めました。私はその場にいたのに、声をかけられることもなく、ただ、その場面を「見せられる」側だった。
私のクラスの子たちは、あのとき何を感じたでしょうか。そして私は、何を感じたか──「あなたを担任として信頼していない」そう言われたように感じました。
大人たちのそうした態度が、私の存在価値を少しずつ削っていきました。次第に、自分自身を信じることさえ難しくなっていったのです。



職員室にて他の職員がいる前で、とあるベテラン教員に「あなたのクラスは学級崩壊していると糾弾されてしまいました…。翌日から出勤の足取りが重くなったのことは今ではいい思い出です(笑)
それでも教師を辞めなかった理由
子どもたちの笑顔と、静かな使命感
それでも心が完全に折れなかったのは、教室の中に確かにあった、子どもたちの存在でした。朝の挨拶、ふと見せる笑顔、頑張ろうとするまなざし。
「この子たちと、なんとか前を向きたい」
「この教室を、もう一度、あたたかい場所にしたい」
そんな静かな使命感が、私を支えていました。
決して劇的なドラマではありません。でも、その日その日の積み重ねが、心を少しずつ立て直してくれたのです。
「うまくいかない自分」を許す大切さ
私はずっと、「完璧な教師」でなければいけないと思い込んでいました。でも、違ったのです。
うまくいかない日があってもいい。間違ってしまう日があってもいい。「それでも子どもたちの前に立ち続ける」その姿こそが、子どもたちにとって本当の教育なのだと、気づくことができたのです。
学級崩壊から立ち直るために必要だった考え方
成功より「リカバリー力」が大事
学級崩壊を経験して、私ははっきりと知りました。教師にとって大事なのは、「一度も失敗しないこと」ではありません。
転んだときに、どう立ち上がるか。間違えたときに、どう修正していくか。それを子どもたちに見せることの方が、よほど価値があるのだと。
リカバリーできる大人の背中を見せる。それが、教室の空気を少しずつ変えていく力になることを学びました。
「子どもファースト」の本当の意味に気づく
そしてもう一つ。「子どもファースト」とは、単に子どもに優しくすることではありませんでした。
子どもたちが未来を生きていくために、時にはぶつかりながらも、共に成長しようとする覚悟。その本気さこそが、子どもたちの心に伝わるのだと、痛感しました。
子どもたちのために、私は何度でも立ち上がろう。心から、そう思えるようになったのです。
学級崩壊を経験した今だから言えること
完璧な教師なんていない
今、振り返って思うのは──完璧な教師なんて、最初からどこにもいないということです。
どんなに立派に見える人でも、どこかで悩み、間違え、迷いながら歩んでいる。それを認めたとき、私は初めて、「教師である前に、一人の人間」として、自分を許すことができました。
あなたが立ち止まらない限り、失敗は「途中経過」
学級崩壊も、左遷も、自己嫌悪も──すべては「失敗」ではありませんでした。
まだ道の途中。まだ、成長の途中。あなたが立ち止まらない限り、今の苦しみも、未来へ続く「過程」なのだと、私は心から信じています。
まとめ
教師として歩き続けるなかで、私は気づきました。学級崩壊は、私を壊したのではなく、むしろ本当の意味で「教育とは何か」を問い直す機会をくれたのだと。
今、苦しんでいるあなたへ。どうか、自分を責めすぎないでください。
うまくいかない日があってもいい。誰かに認められなくても、あなたがあなたであり続けることに、価値があります。
まずは、今日一日を乗り越えましょう。そしてまた、明日を迎えにいきましょう。
あなたが教師を続けることは、きっと、誰かの希望になります。
(もしよければ、あなたの体験もコメントで教えてください。一緒に、歩き続けましょう。