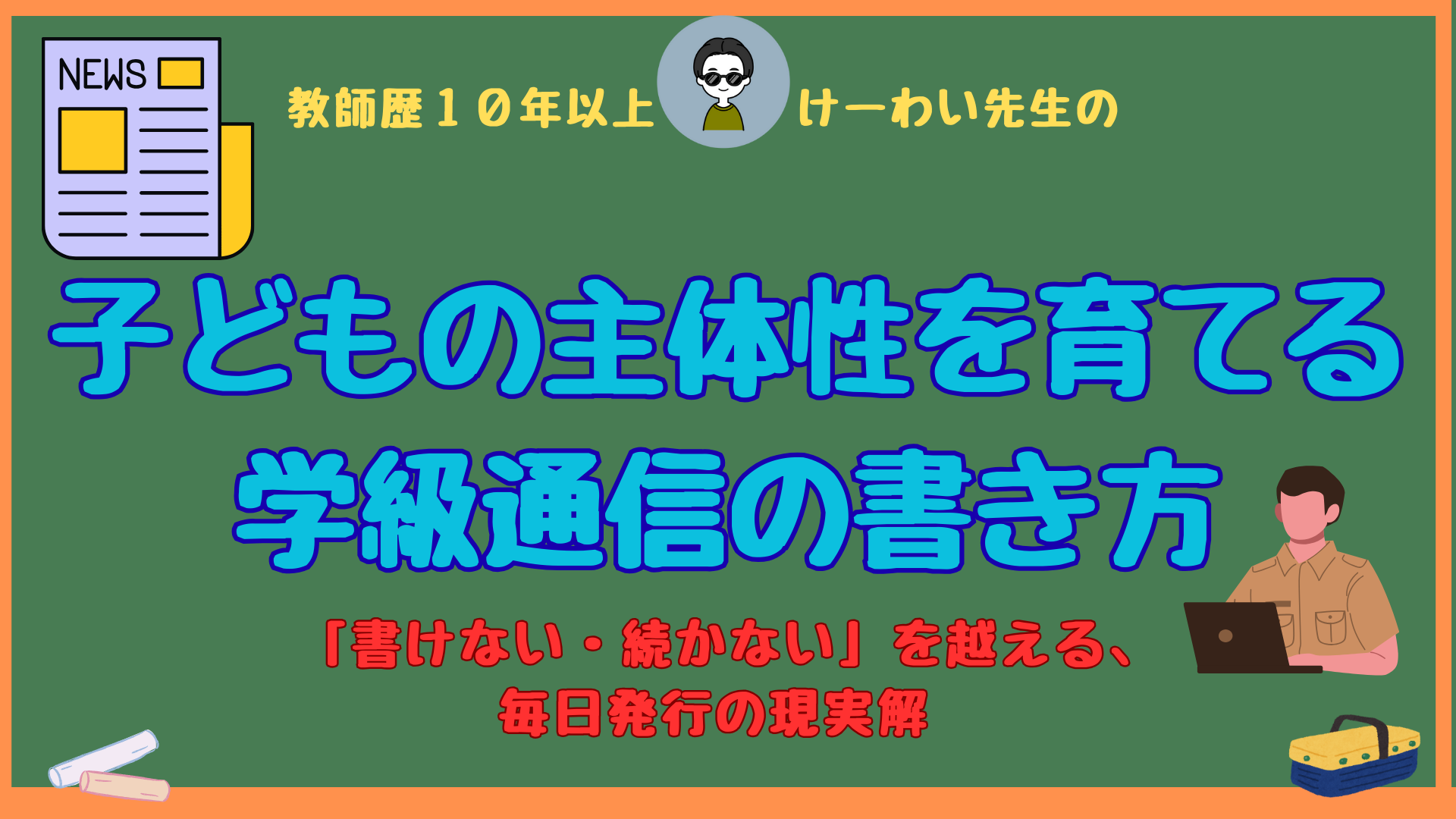「学級通信、最初は意気込むのに続かない」——多くの先生のリアルです。
実は、書けない日があるのは当たり前。大切なのは“完璧より継続”の設計です。
私は毎日発行・写真多め・ふりかえりジャーナル併用で続けてきました。
結果、通信は“子どもの主体性を映す鏡”になり、家庭との信頼が深まり、私自身の文章力(論作文)も伸びました。
本記事では、読者の「書けない・続けられない」を吹き出し対話で受け止めつつ、テンプレ運用/時短設計/節目メッセージ/100号の意味まで、すぐ真似できる形でお届けします。
参考書籍
導入:そもそも「書けない人が多い」
 新卒先生A
新卒先生A最初はやるぞ!ってなるんですが…だんだん書けなくなります。



わかります。書けない日があるのは普通。だから、“毎日出せる仕組み”から作りましょう。
通信の目的は「完璧な文章」ではなく子どもの学びを可視化すること。
続ける鍵は型・時短・分業(子どもの言葉)。
私の結論:毎日発行×写真多め×ふりかえり



毎日はハードル高そう…。



だから写真で7割伝えるんです。文章は短くてOK。さらに、ふりかえりジャーナルで“子ども自身を共著者”にします。
写真=表情・手元・関わりでプロセスが一瞬で伝わる
ふりかえり=子の言葉が家庭へ届き、再び子へ返る循環が生まれる
サンプルテンプレ
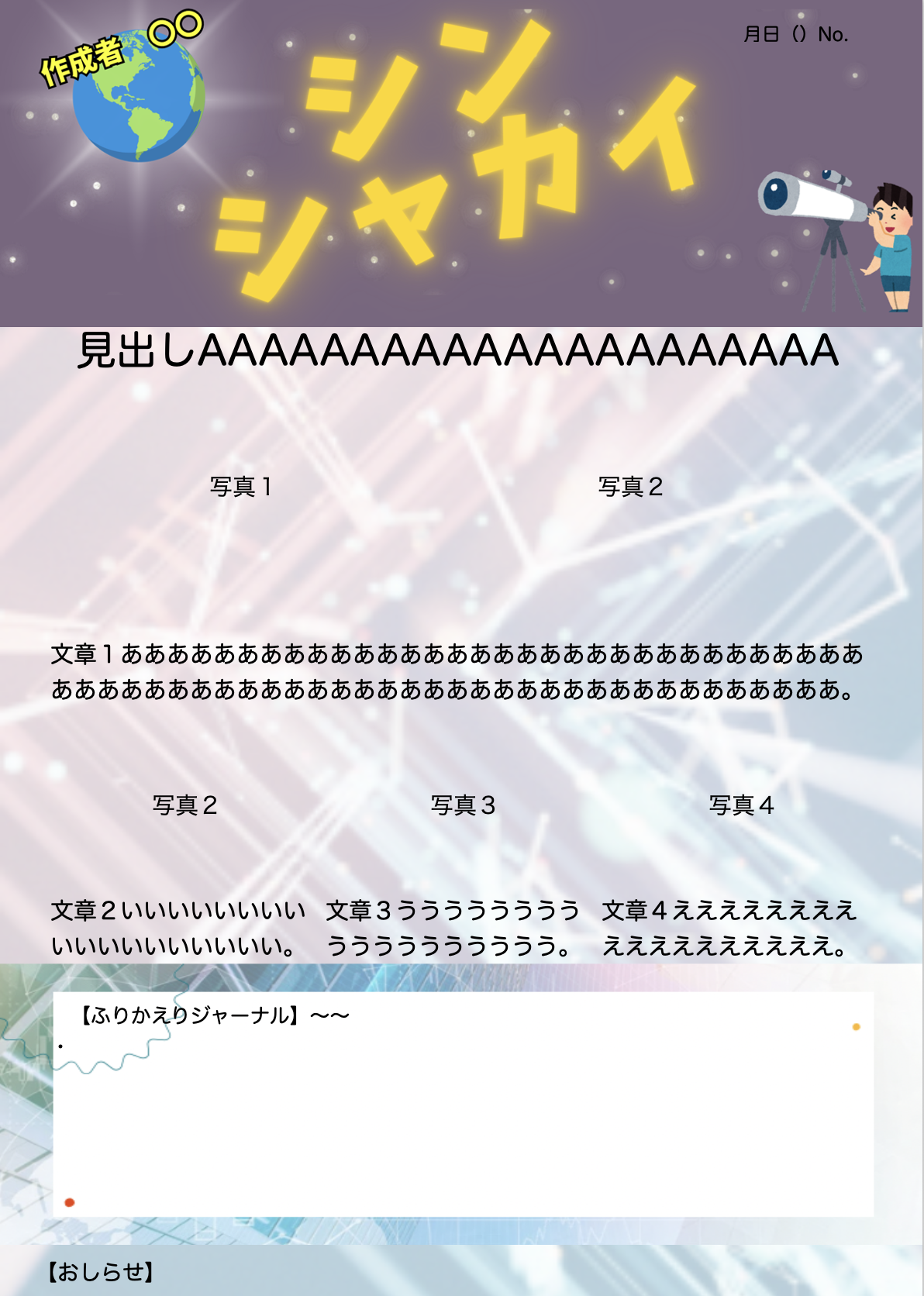
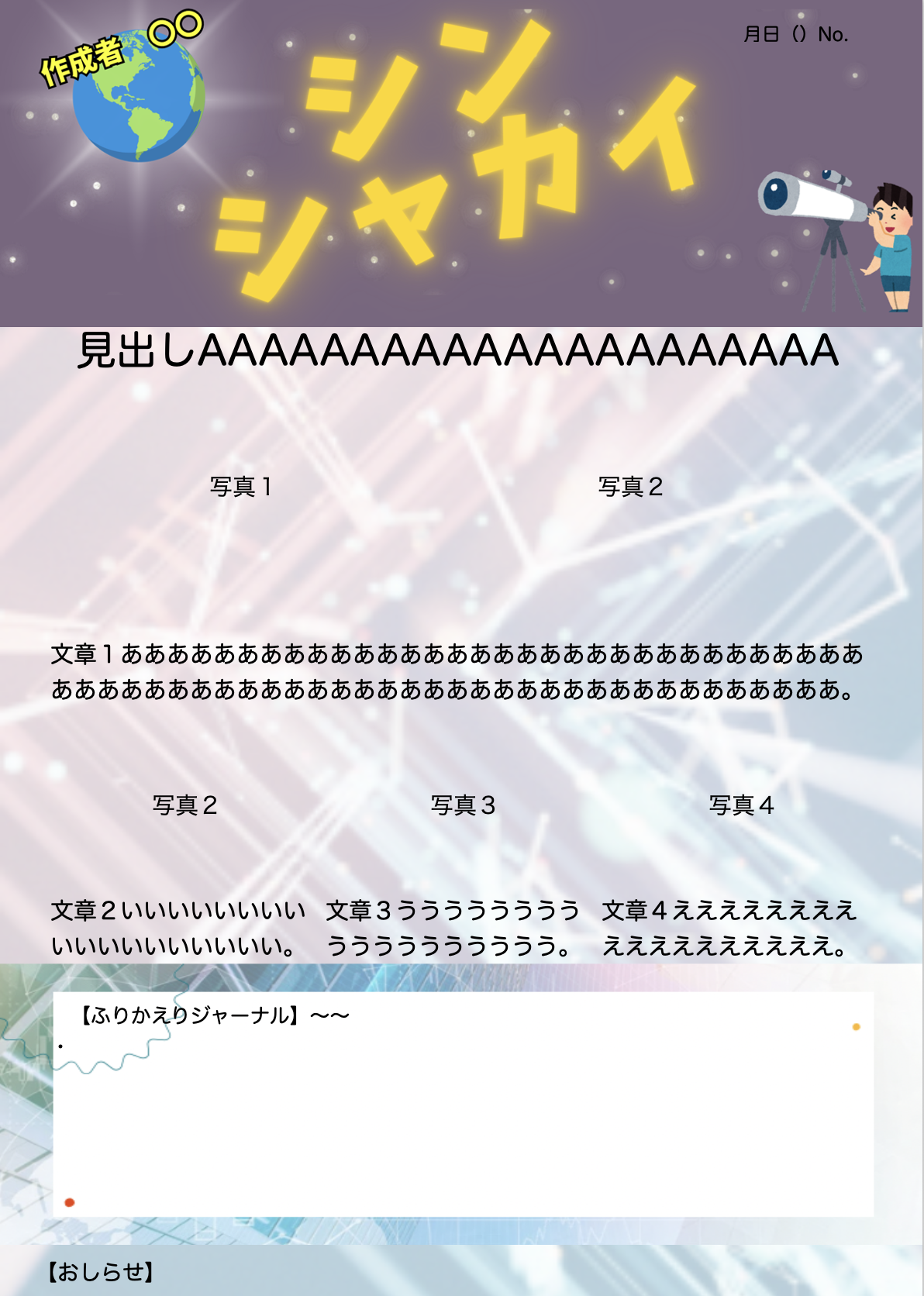
構成要素
見出し(今日のテーマ/一言)
写真1〜4(様子メイン・動きのある瞬間)
短い本文(30〜90字:子の言葉+価値づけ)
ふりかえりジャーナル(子どもの一行感想)
おしらせ(家庭連絡・持ち物・明日の見通し)
👉 ふりかえりジャーナルの詳しい意義と実践は、こちらにまとめています。
➡ 振り返りジャーナルの意義と実践法
節目メッセージ:毎日は“様子”、節目で“先生の声”



想いも書きたいんですが、毎日は難しい…。



節目だけ濃くで十分。はじまり/折り返し/学期末に“手紙”を書いています。
手紙例:
学校が始まり、あっという間に3日が経ちました。長い休みも、正直わるくはありません(趣味のアニメを楽しめるので…?)。でもやっぱり、元気な子どもたちと過ごす日々は、かけがえのないものだと感じています。
趣味の時間はもちろん楽しいです。けれど、子どもたちが成長していく過程を見届けられることは、その何倍もすばらしいことです。もちろん、その「成長」にたどりつくまでには苦労があり、今後も続いていきます。それでも、この3日間で「教師」という仕事のやりがいをあらためて感じました。そして同時に、夏休みの間、家庭で子どもたちと向き合ってくださったお家の方へのリスペクトの思いを強くしました。感謝しています。
日常=子どもの姿中心
節目=先生の理念・感謝・見通しを言語化
先生も育つ:毎日の「起案」が文章力を鍛える



通信って、子どもと保護者のためのものですよね?



もちろん。でも実は先生の文章道場にもなります。
私は何度も落ちていた教員採用試験の論作文で、通信の積み重ねが評価アップに直結。
子どもの具体→教育観→示唆の流れが自然に書けるようになり、合格へ。
写真→要約→見出し→価値づけ=毎日の小論文訓練
通信は子も育て、先生も育てる。
「書けない・続けられない」を越える時短5則
時間上限15分:写真選定5/要約5/出力5
語彙の“価値語辞書”を作る:例)聴き合い/役割交代/見通し/試行錯誤
曜日コーナー化:月=めあて/火=今日の主役/水=協働の瞬間/木=ふりかえり特集/金=一週間のベスト
写真は“動きが写る”:視線・手元・関わりを優先(顔NGは後ろ姿・手元・作品で等価代替)
薄号を恐れない:「写真2枚+一言」も立派な1号



最近はAIに文章生成を手伝ってもらっています。
100号というステータス



100号って、やっぱり特別ですか?



はい。信頼と学びの蓄積の可視化です。



「私、何号に載った?」(自分史の索引)



私にとって我が子の一年の成長アルバムです。



実践と文章のポートフォリオ(研修・論文の土台)
記念号の仕掛け例
子どもの「一言ベスト」再掲
協働の名場面3選(写真)
保護者への感謝レター
次学期の「約束」3本
よくあるつまずき→即レスQ&A
Q. 反応が薄い日がある
A. 節目メッセージで“声かけのきっかけ”を一行用意。「家で一言感想を伝えてください」など。
Q. ネタ切れ
A. 片付け・役割交代・話し合いの態度・掲示物…“学びのプロセス”は無限。子の一言を拾う。
Q. 写真の扱いが不安
A. 同意の範囲・NGリストの管理。外部再配布不可を明記。NGは手元・後ろ姿・作品で代替。



ちなみ毎日出し続けると、200号になります。
まとめ:今日の一枚が、明日の100号へ



完璧じゃなくていい。まずは出す、ですね。



そうです。【継続は設計でつくる】もの。
通信は“学びの鏡”であり、先生の道場でもあります。
今日の一枚が、子どもの主体性を照らし、家庭の信頼を育み、あなたの言葉を鍛えます。
さあ、きょうも1号。 そして、いつか胸を張って100号へ。
関連記事
先生も育つ!日々の通信が論作文の力になる理由 ※準備中
振り返りジャーナルの意義と実践法 ※準備中