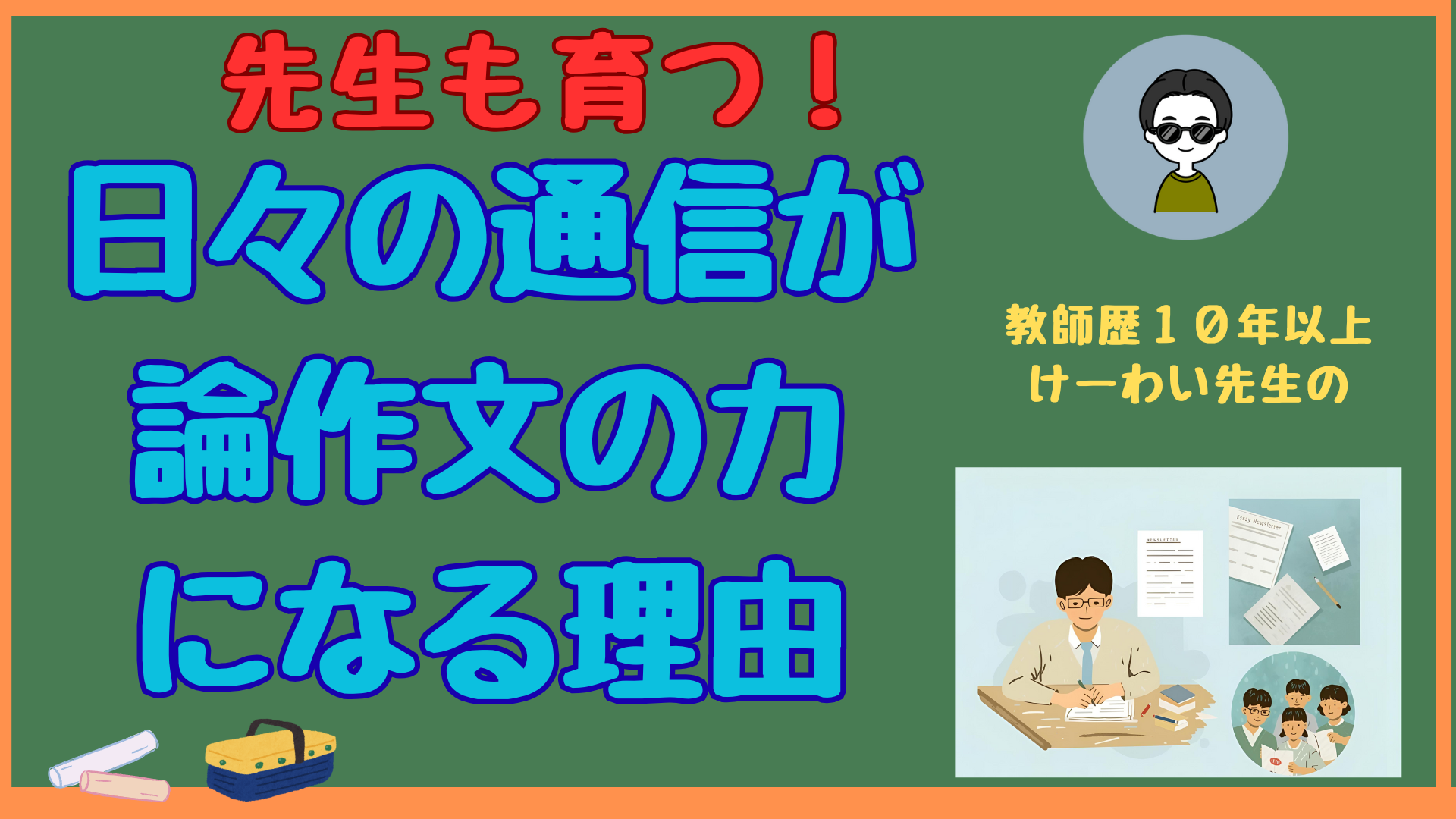導入
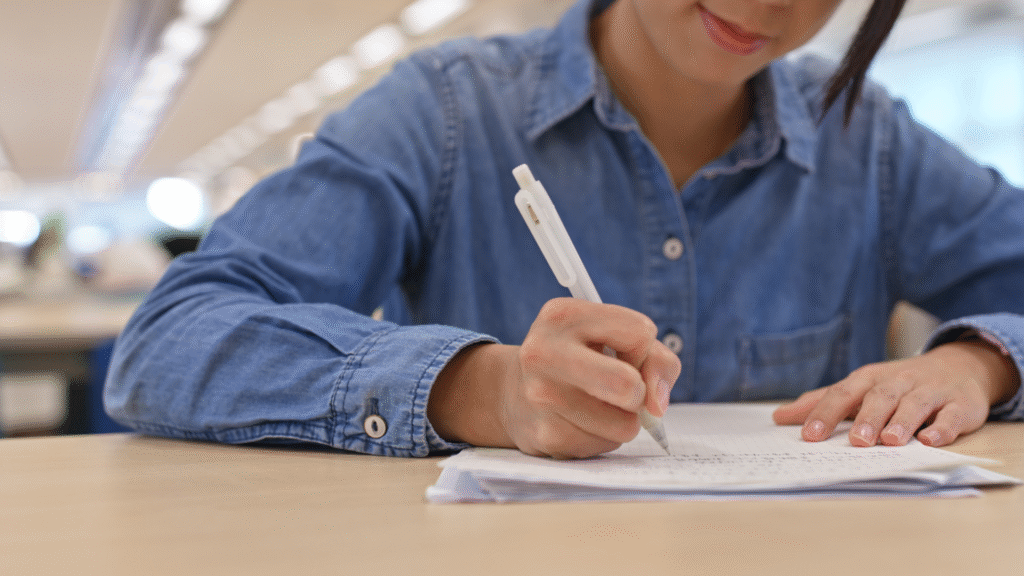
「学級通信は、お知らせを保護者に伝えるだけ」
—そんなふうに考えていませんか?
実は、通信は先生自身の“文章力”を育て、論作文合格にも直結するトレーニングになる
私はこの事実を、身をもって体験しました。
7回以上も教員採用試験に落ち、特に論作文の評価が低かった私。
でも、学級通信に力を入れ始めたことが転機となり、文章の質が変わり、ついに合格を勝ち取ったのです。
筆者の背景|不合格を重ねた常勤講師時代
 新卒先生B
新卒先生Bまた不合格…。論作文に“説得力不足”って書かれてる。
どう直したらいいのか分からない…。
7回以上落ち続ける中で、自分の限界を感じることもありました。
授業や子どもとの関わりには自信があっても、「文章で伝える力」が弱いと評価され続けたのです。
転機|通信に救われた一言



学級通信を書くといいよ。
子どもの姿から教育の意味までつながってる。
論作文も同じように書けばいいんだよ。
この一言でハッとしました。
「子どものエピソード→教育的な意味→示唆でまとめる」
まさに論作文と同じ構造だったのです。
そこから、通信を書くこと自体を「小論文練習」と位置づけ、毎日書き続けました。
通信が論作文力を鍛える理由
子どもの具体→教育観→示唆の流れがそのまま論作文
通信の基本構造=論作文の型
通信は「子どもの出来事」を描き、「教育的意味」を示し、「未来への一言」で締める。
この流れは論作文の王道そのものです。
保護者に伝わる=読み手を意識する訓練
論作文は「採点者に届く文章」が求められます。
通信は日常的に保護者を対象に書くため、「どう書けば伝わるか」を自然に意識できる環境です。



“先生が指導しました”よりも、
“子どもたちが工夫して取り組みました”の方が
伝わると気づきました。
起案チェック=毎日の添削練習
上司の起案チェックは、いわば無料の添削。冗長な表現はカットされ、曖昧さは直される。
これを毎日繰り返すうちに、文章の精度が磨かれていきました。
実践編|明日からできる通信の工夫


お知らせ+子どもの頑張り+教育的意味 を必ずセットで書く
一文一義を意識(一文に一つの内容だけを書く)
教育観はワンフレーズで締める(例:「協力は日常の中で育つ力です」)
時間を区切って書く(15分で仕上げると推敲力が上がる)
主語を子どもにする(「先生が〜」より「子どもが〜」)



“子どもが育った姿”で書くと、
保護者も“わが子の変化”として受け取ってくれました。
保護者・上司からの声
「通信で、うちの子の頑張りがよく伝わってきます」
「文章が分かりやすい。あなたの通信は読みやすいね」
「論作文も通信みたいに書けば合格できる」
通信に力を入れると、自然と周囲の評価も変わる。
まとめ|通信は「子も育て、先生も育てる」
学級通信は、保護者にとって子どもの成長を知る窓口。
けれど同時に、先生にとっては“論作文の道場”でもあります。
7回不合格から合格を勝ち取った私が証明しています。
通信は、子どもを育て、保護者をつなぎ、そして先生自身をも育てる。
——次の通信で、“教育観のひとこと”を添えてみませんか?
関連記事
子どもの主体性を育てる学級通信の書き方—「書けない・続かない」を越える、毎日発行の現実解—
振り返りジャーナルの意義と実践法 ※準備中