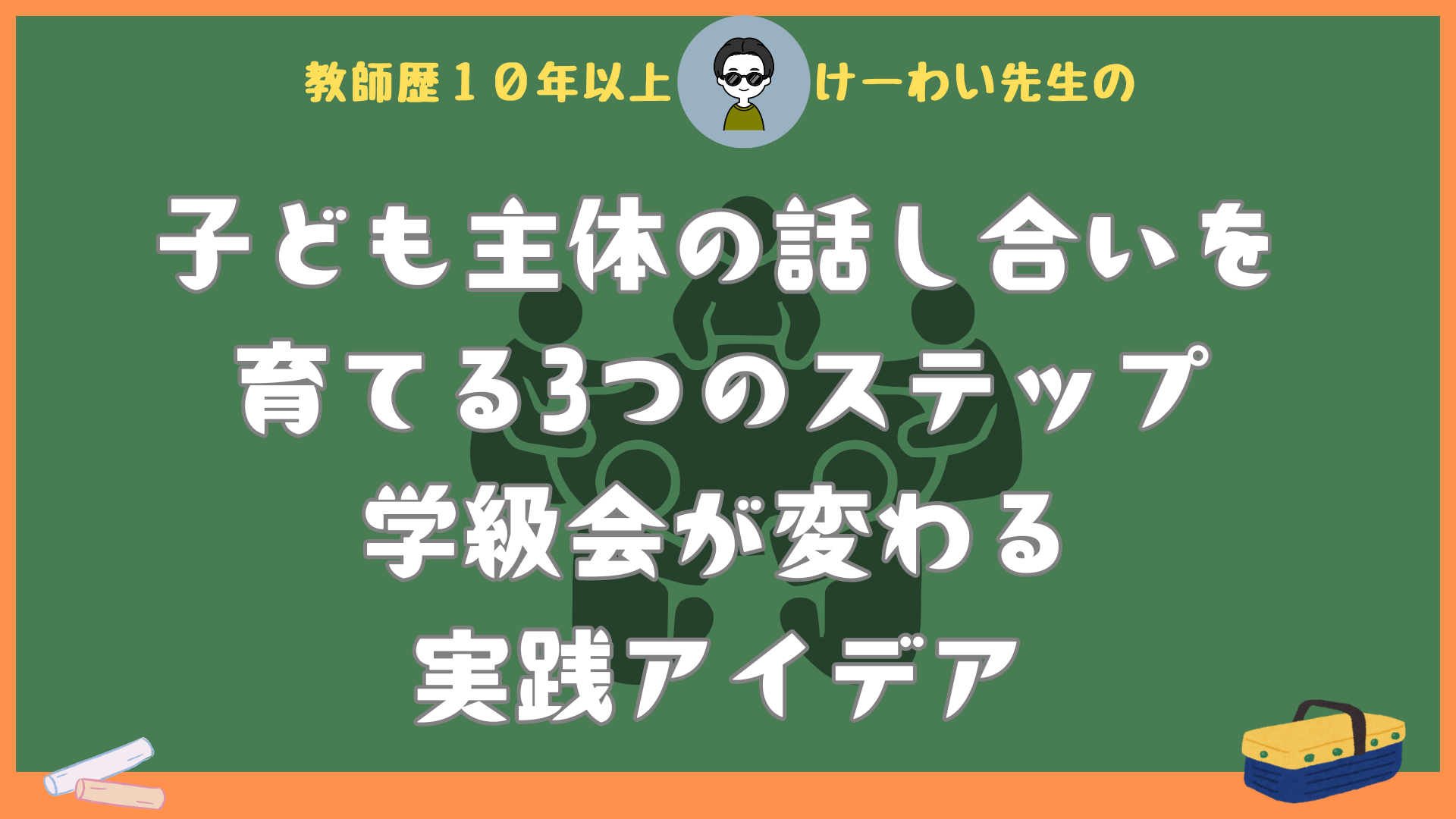【導入】話し合いがうまくいかないのは「子どもが主体じゃないから」?
「話し合い活動ってやってるけど、どうも盛り上がらない…」
「司会はいるけど、結局先生が全部まとめてる…」そんな風に感じたこと、ありませんか?
実はこれ、私自身が長年悩んできたテーマでもあります。
話し合い活動を導入しても、形式だけになってしまい、子どもの意見が広がらない…。
でもあるとき、「そもそも“問い”の出発点が子どもじゃなかった」と気づいたのです。
この記事では、子ども主体の話し合い活動を育てるために、私が実践して効果を感じた3つのステップを紹介します。
【筆者の背景】「話し合い=先生主導」だった過去
私は長く小学校で担任を務めていますが、正直に言うと、昔の話し合い活動はほとんど“進行台本”でした。
「司会:◯◯くん、よろしくお願いします」から始まり、最後は「先生のまとめコメント」で締める。
子どもたちは“参加している風”だけで、自分ごととして捉えていなかったのです。
📢 子どもたちは“参加している風”だけで、自分ごととして捉えていなかったのです。
ところが、ある年の学級で、子どもたちの中から自然に「話したいこと」が出てくるようになった経験がありました。
それ以来、「話し合いはスキルではなく、文化なんだ」と考えるようになったのです。
【本題】子ども主体の話し合いを育てる3つのステップ
① 「問い」を共有する
話し合いの出発点が「先生の課題提示」だと、どこか他人事になりがちです。
 けーわい
けーわい 「先生が決めたことをどう思うか」ではなく、
「自分たちで決めたいこと」からスタートするといいでしょう。
例えばこんな方法があります:
教室に「もやもやボード」を設置
ふせんに日々の困りごとや気になることを書いて貼る
それをもとに「今日の話し合いテーマ」を子どもが選ぶ



給食の時間がうるさいの、どうしたらいい?



当番の仕事が多すぎると思う!
② 話し合いの型を学ぶ
子どもたちは、話し合いのやり方を“なんとなく”で学んでいるわけではありません。
話し合いを進めるには、司会の進行スキル、話を聞く姿勢、相手の意見を受けてつなげる力などが必要です。



はい、じゃあ○○さんの意見に“たして”言える人いますか?



ぼくも、給食の時間は静かにしたいと思います。
こんな“型”を教える時間を、授業の一部に組み込みましょう。
おすすめは以下のような方法です:
ロールプレイ形式で話し合い練習(テーマは軽めでOK)
話し合い振り返りジャーナルの導入
評価の見える化(話し合いカードやルーブリック)
③ 任せる“勇気”をもつ
ここが一番難しくて、一番大切なポイントです。
☝️ うまくいかなくても、子どもに任せることをやめない。
進行が止まっても、先生が口を出しすぎない
まとめが弱くても、子どもたちに問い返してみる
意見が出なかったら「今日の話し合いはこれでいいの?」と問いかける



「子どもたちを信じて、場を手放す」
それが、“本当に子どもが主体になる”瞬間を生み出します。
また、全員がいきなり司会をできるわけではないので、
「司会見習い」制度
「書記・タイムキーパー」などのサポート役の設定
1人1回は小テーマでの進行を経験
…など、誰もが主役になれる仕掛けを意識的に用意しておくと◎です。
【実践編】日々の学級経営の中で育てる工夫



話し合いの力を育てるのは、特別な時間だけじゃありません。
▷ 朝の会・帰りの会を“話し合いの場”にする
「朝の一言テーマ」や「帰りの反省会」など、小さな話し合いの積み重ねが、話す・聞く力を鍛えます。
▷ 係活動や当番活動で話し合いを活用
係や当番の課題も、子どもたち同士で解決策を話し合うように促しましょう。
▷ 話し合いジャーナルを導入
以下のようなフォーマットで、毎回の話し合いをふりかえるようにします。
| 今日のテーマ | 意見を言えた? | 印象に残った意見 | 次回に向けて |
|---|---|---|---|
| 給食の時間の過ごし方 | ◯ | 「静かすぎても話せない」って意見 | 賛成意見ばかりだった。反対も出したい |



意見は言えたけど、反対意見にうなずくだけだった…。



次は“つなぐ言葉”を使ってみたい!
【まとめ】語り合える教室は、子どもが育つ教室
話し合いが上手にできるかどうかより、
子どもが本気で語り合おうとする“関係性”があるかどうかが大切です。
先生がまとめず、子どもたちがモヤモヤを持ち寄って、ぶつかりながら決めていく。
そのプロセスの中にこそ、主体性や民主的な力が育まれます。



私たち教師ができるのは、“正しい答え”を与えることではなく、
語り合いたくなる場と関係性を耕すことかもしれません。
📚 関連記事リンク
👉 話し合いを振り返る「ふりかえりジャーナル」活用法(準備中)
👉 学級経営のルールづくりに悩んだら読む記事(準備中)
👉 係活動が劇的に変わる!子どもが主役になる仕掛けとは?(準備中)