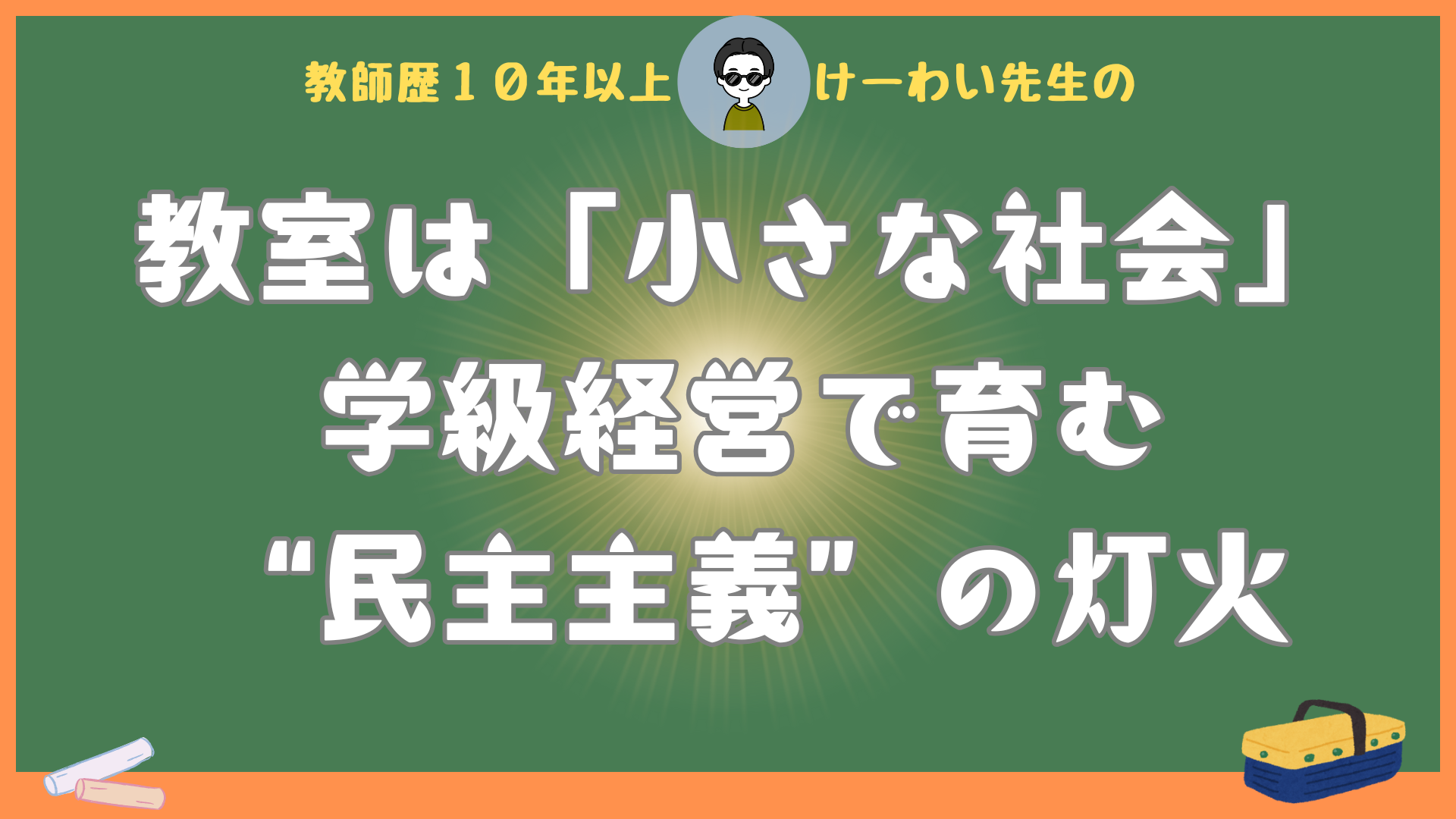迷いの始まり:「先生、このルールって、なんのためにあるの?」
 児童A
児童A先生、このルールって、なんのためにあるの?



…。
その子どもの、まっすぐで曇りのない眼差しに、私は言葉を失いました。
毎日を忙しく走り抜ける中で、いつの間にか当たり前になっていたルールや仕組み。それは本当に、この子たちの未来を照らすためのものだったのでしょうか。
教室は、知識という荷物を下ろす場所ではありません。
それは、子どもたちが初めて出会う「小さな社会」。意見をぶつけ、対立し、それでも共に生きていく術を学ぶ、人生最初の実験室です。
今回は、「学級経営=民主主義の実践」という視点から、私自身が迷い、問い続け、そしてようやく見つけた“本質”の光についてお話しします。
教室づくりの原点に立ち返ったあの日
教員になりたての頃、私は「完璧な管理者」であろうとしました。
明確な指示と厳格な決まりで、クラスを静かに整えることこそが、“良い学級経営”だと信じていたのです。
けれど、ある日、ふと気づいてしまったのです。
その整然と「うまくいっている」ように見えたクラスで、子どもたちの瞳から、考える光が消えていたことに。
意見を言わない。反対しない。疑問を持たない。
それは、従順な“良い子たち”なのではなく、自らの思考を停止してしまった子どもたちの姿でした。
私は、自らに問い始めました。
「この静けさは、本当に平和なのか?」
「このルールは、誰が、何のために作ったのか?」
教室は小さな社会。ならば、ここで育てるべきは、盲目的な服従ではなく、自ら考え、行動する民主主義の“根っこ”に違いない。そう、心に誓ったあの日が、私の原点です。
『図書館ライオン』が教えてくれたこと
私はときどき、『図書館ライオン』という絵本を思い出します。
ルールに忠実だった司書さん。
けれどある日、ライオンが図書館に入ってきて、
「ルールを守ること」と「誰かを思いやること」の間で、激しく揺れ動きます。
教室の中でも、同じような瞬間が訪れます。
全員が守るべきルールが正しいのか、
それとも、目の前の子どもの感情や事情を優先すべきか。
その狭間で悩み、立ち止まり、問い続ける時間こそが、民主主義を形づくっているのかもしれません。
学級経営とは、単なる管理ではなく、「愛と秩序のバランスを、子どもと共に探求する営み」なのです。
民主主義=話し合い、ではない。それは「納得」の土壌
多くの先生が、「話し合い活動=民主的な学級」だと考えがちです。私もそうでした。
しかし、本当の民主主義とは「話し合うこと」の結果ではなく、“決まったことに心から納得して従える仕組み”を育てることです。
多数決は、時に少数派を置き去りにし、心に影を落とします。
大切なのは、「どうやって決めたか」というプロセスに、自分も確かに関われたという実感。
この「プロセスへの納得」という土壌に、信頼と協働の芽が育つのです。
結びに:教師もまた「小さな社会」の市民として
子どもたちにとって、教室は「最初の社会」。
その問いかけに、まっすぐに応えられる教室を、私たちはつくれているでしょうか。
指示を待つのではなく、自分で考えて決めて動く。
対立しても、対話を通じて共に最善を見つける。
そんな市民の力を育てるため、教師は「完璧な管理者」の鎧を脱ぎ、子どもと共に悩み、問い、決めていく“一市民”として教室に立つ必要があります。



完璧な答えなんて、きっとない。
でも、子どもたちと一緒に考え続ける限り、教室の灯は消えない…。
📚関連記事もあわせてどうぞ
子ども主体の話し合い活動を育てる3つのステップ(準備中)
「静か=いい子」じゃない!クラスに“声”を取り戻す方法(準備中)
民主主義と学びの関係を考えるおすすめ書籍5選(準備中)