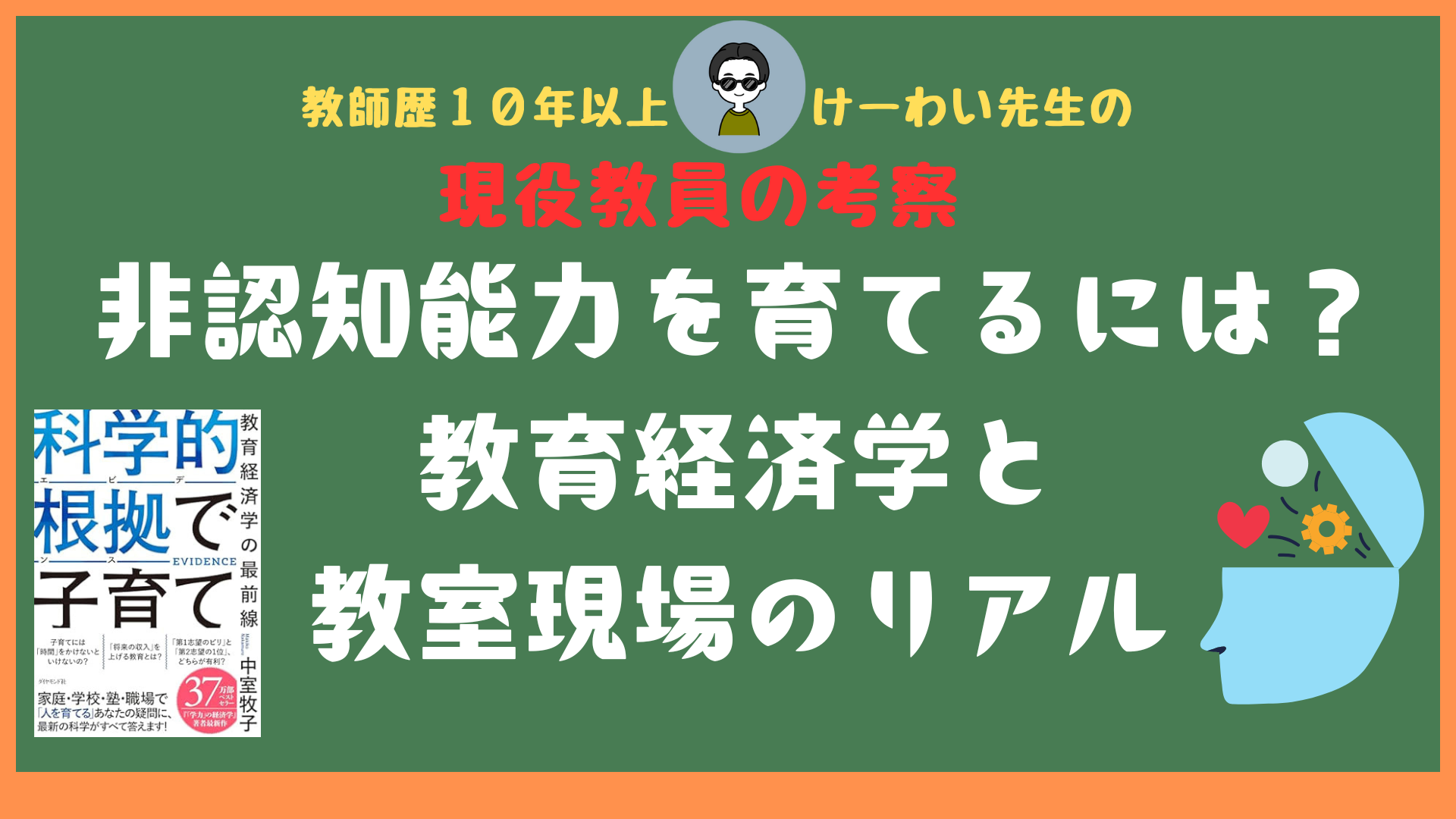「やり抜く力」「忍耐力」「自制心」――これらは“非認知能力”と呼ばれる、テストには出ないけれど人生に深く関わる力です。
最近の研究では、非認知能力が将来の収入や学歴、さらには幸福度にまで影響することが明らかになっています。
 けーわい
けーわい学力があるのに、社会に出てつまずいてしまう子って、
実は非認知能力が足りなかったりするのかも…?
けれど、この大切な力は、親のかかわり方や家庭環境によって“格差”が生まれやすいのも事実。
「うちの子、すぐあきらめる」「根気がないのは性格?」――そんな不安や疑問はありませんか?
本記事では、教育経済学の知見と小学校教員としての実体験をもとに、非認知能力の重要性と育て方のヒントをお届けします。
“学力だけじゃない”子育てと教育のあり方を、一緒に考えていきましょう。
【筆者の背景】教育現場で感じた“見えない力”の大切さ
私は現役の小学校教員として、毎日多くの子どもたちと向き合っています。
そしてここ数年、「学力」よりも「非認知能力」の差のほうが深刻だと感じる場面が増えてきました。
すぐに諦めてしまう子、他者とうまく関われない子、自分の感情をコントロールできない子――。
その背景には、家庭環境の違いや関わり方の“格差”が大きく関係していることも多いのです。
一方で、「人に教える」「チームで取り組む」活動の中で、グッと伸びる子がいることにも何度も出会ってきました。
これは教育経済学で語られる「ピア効果(教え合いの学習効果)」と一致していて、私自身が最も注目しているポイントです。
【本題】非認知能力がもたらす“目に見えない将来の差”
「うちの子はちょっと不器用だけど、まじめでコツコツ頑張るタイプです」そんな子どもが、実は将来“じわじわと大きな成果”を出す――。
これはただの希望的観測ではなく、データが裏付けている事実です。
教育経済学では、「非認知能力」が将来の収入や学歴、さらには社会的成功にまで強い相関を持つことが、複数の研究で明らかにされています。
では、具体的にどんな非認知能力が「人生の土台」になっているのか?
ここでは、将来の収入アップと関連の深い、3つの非認知能力を詳しく紹介します。
● 将来の収入を上げる「3つの非認知能力」
① 忍耐力(がまん強く取り組む力)
目の前の誘惑に負けずに、コツコツ努力を続けられる力です。
たとえば、宿題やピアノの練習を「今はやりたくないけど将来のためにやる」と判断できる子は、忍耐力が育っています。
この力があると、途中で投げ出さずに長期目標に向かって努力し続けることができるため、学力や進路、仕事にも好影響を与えます。
② 自制心(感情や衝動をコントロールする力)
怒りや悲しみ、不安などの感情を、他人や環境のせいにせずに自分で調整できる力です。
友達とケンカしても落ち着いて対話できる子、自分のミスを冷静に受け入れられる子は、自制心が育っています。
社会に出ても、チームワークや対人関係においてこの力は非常に重要です。
③ やり抜く力(失敗しても続けられる力)
一度や二度の失敗で諦めず、成功するまで工夫しながら粘り強く取り組む力です。
近年では「グリット(Grit)」とも呼ばれ、人生全体の満足度や達成感にも深く関わる力として注目されています。
💡補足:「学力」はある意味“短期勝負”ですが、非認知能力は“長期的な人間力”。だからこそ、目先の成績にとらわれず、土台として育てたい力です。
【家庭で生まれる“非認知能力格差”のリアル】
非認知能力は、すべての子どもが平等に持って生まれるわけではありません。
そして、育てられる環境によっても大きく差が出てくるのが現実です。
家庭という最も身近な環境が、子どもの将来を左右する“土台”となるからこそ、改めてその重要性に目を向ける必要があります。
● 時間投資は「年齢が低いほど」効果が高い
教育経済学では、子どもの発達への「時間投資」は幼児期のほうがリターンが大きいとされています。言い換えれば、年齢が上がるにつれて、同じ努力でも効果は薄くなるということです。
● 家庭環境の“差”が非認知能力にも表れる
しかし現実には、忙しい家庭・一人親世帯・親自身に余裕がない家庭ほど、この“時間投資”が難しくなります。



仕事と家事で精一杯…。
正直、子どもとの会話は最低限しかできていません。
その結果、親自身の余裕の有無によって、子どもたちの見えない格差が広がってしまうのです。
【学校で非認知能力を育てるには】
学校は、家庭と並ぶもう一つの重要な成長の場です。
特に非認知能力のような“見えにくい力”は、日々の人間関係や集団活動の中で育まれるため、学校の役割は非常に大きいのです。
ここでは、学校現場でどのように非認知能力が育てられているのかをご紹介します。
● 思いやりや協力を育てる“日常の教育”
非認知能力は、特別な教材や授業ではなく、日常の人間関係の中で育ちます。
たとえば、困っている友達を助ける、話を最後まで聴く、順番を守るといった行動の積み重ねが、思いやりや自制心を育てるのです。
● ピア効果を活かした“教え合い”の学習
私が特に推したいのは、「教えることで学ぶ」=ピア学習の導入です。
人に説明するには、まず自分が理解していなければなりません。
だからこそ、「教える」という行為は、学力と非認知能力の両方を同時に伸ばす強力な学習方法なのです。
● ICTは万能じゃない。でも活用には価値がある
一方、「とりあえずPC使えばいい」という誤解もあります。
ICT活用自体は効果がありますが、それだけで非認知能力は育ちません。
デジタル機器はあくまで“手段”。本質は、人との関わりの中でこそ育まれるのです。
【教員こそ、教育の“核”である】
非認知能力を育てるためには、「誰が教えるか」が極めて重要です。
どんな教材よりも、教員のまなざし・言葉かけ・関わり方が、子どもの自己認識や人間関係に大きな影響を与えます。
ここでは、教員としてできること、そして時に誤解されがちな役割について考えます。
● 習熟度に応じた指導ができる教員の重要性
非認知能力と学力、どちらも伸ばせる教員は本当に少ない。
なぜなら、それぞれの子どもの“今”に合わせた指導力が求められるからです。
私は、学力を伸ばすためにも「教え合い」や「思いやり」を重視した指導をしています。
そうした環境の中でこそ、子どもたちは“本当の力”を身につけていきます。
● 非認知能力を重視する先生が“嫌われる”こともある
しかし現場では、非認知能力を大事にする教員が、親に評価されにくい場面もあります。



通知表で“協力できる”とか“思いやりがある”って書かれても、正直ピンとこないんですよね…。



通知表で非認知能力を表現すると抽象的になりがちなんです…(苦笑)
【まとめ】「目に見えない力」が、子どもの未来を支える
🎯 本記事のハイライト
学力も大事
でも、それ以上に「やり抜く力」「思いやる心」「自分をコントロールする力」は一生の武器になる。
教育経済学の研究と、教室での日々の実感が、それを確かに教えてくれます。
子育てに迷ったとき、「何を育てたいのか?」を立ち止まって考えてみませんか?
それはきっと、テストの点数よりも大きな価値があるはずです。
・ 非認知能力は「収入・学歴・幸福度」と深く関係する将来の“土台”
・ これを育てるには、早期の時間投資と家庭・学校の関わりが重要
・ 教育経済学も証明する「教え合い」「思いやり」「自制心」の価値学力も大事。
🔗 関連リンク(設置候補)
▶︎【ピア学習とは?】教室でも家庭でもできる「教えることで育つ」学び方