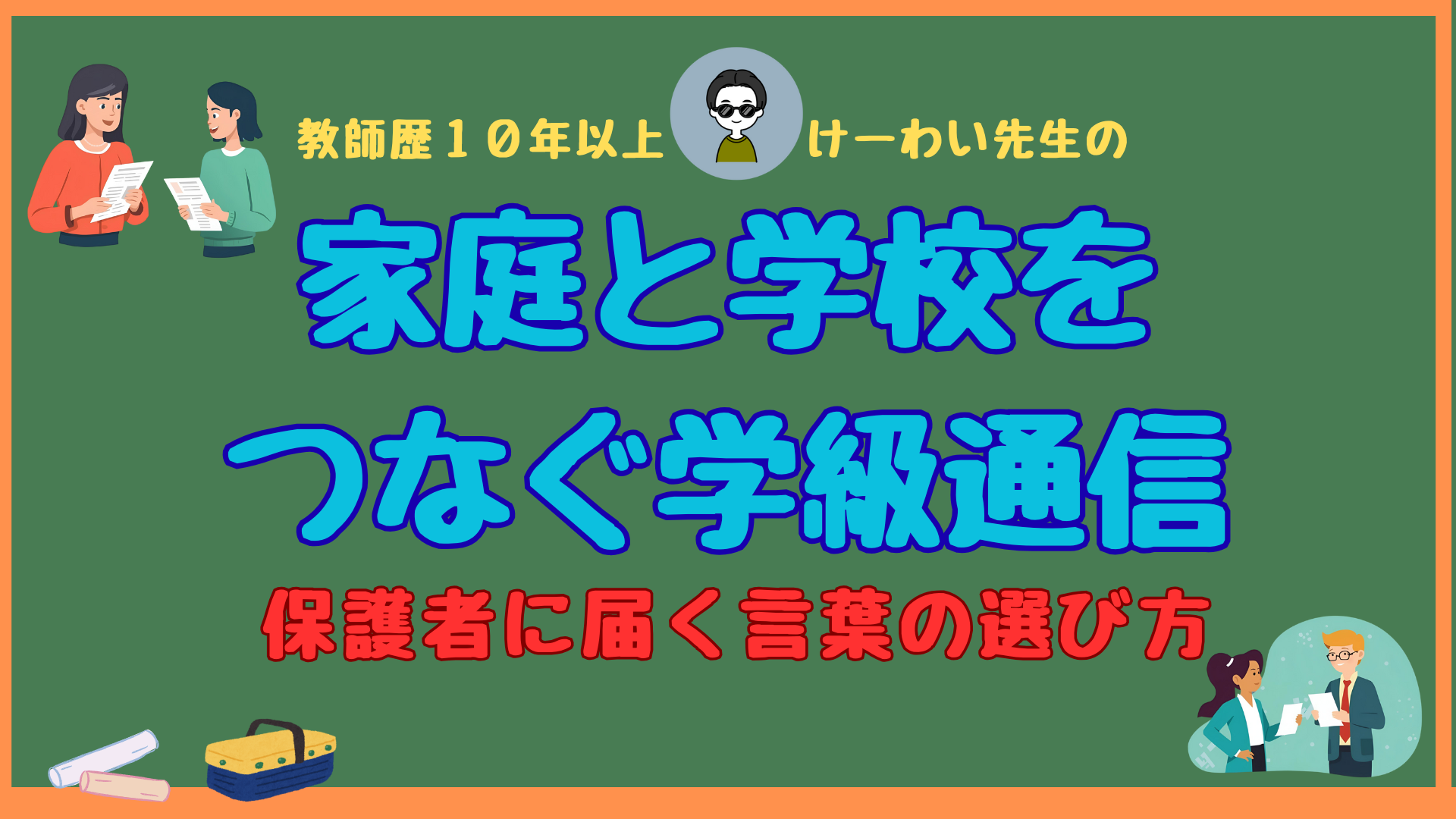【導入】学級通信、こんな悩みはありませんか?

 新卒先生A
新卒先生Aお知らせだけじゃ物足りないから…と思って、実践報告を書いてみるんだけど、どうしても表現がかたくなったり、逆にダラダラ長くなってしまったりしてしまいます。
学級通信は、子どもの姿を保護者に届ける大切なツール。
けれど実践報告が“研究紀要”みたいになってしまう先生も多いのではないでしょうか。
大切なのは、平易な表現で“わが子の姿”を伝えることです。
【筆者の体験談】研究報告風から“やさしい通信”へ
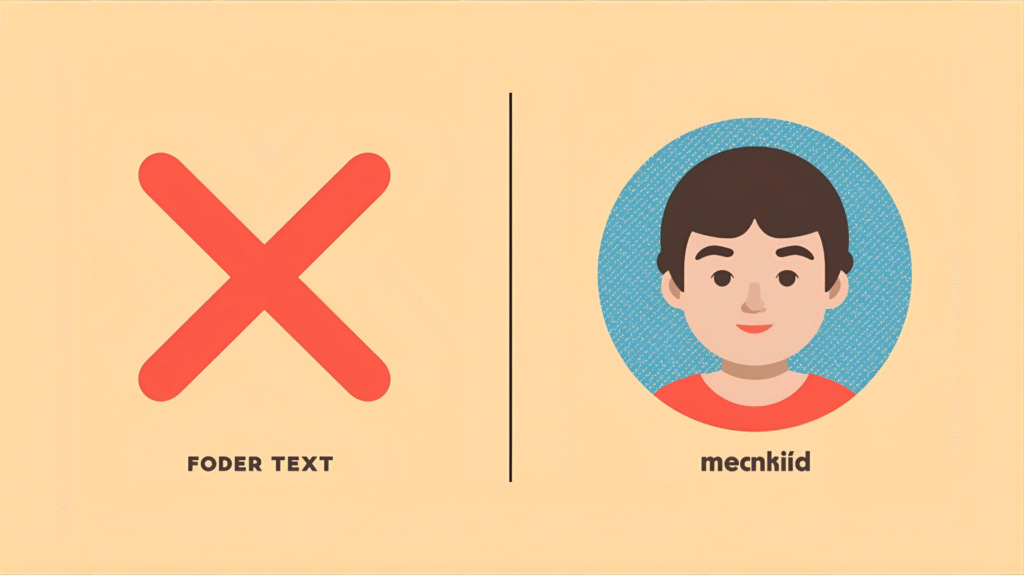
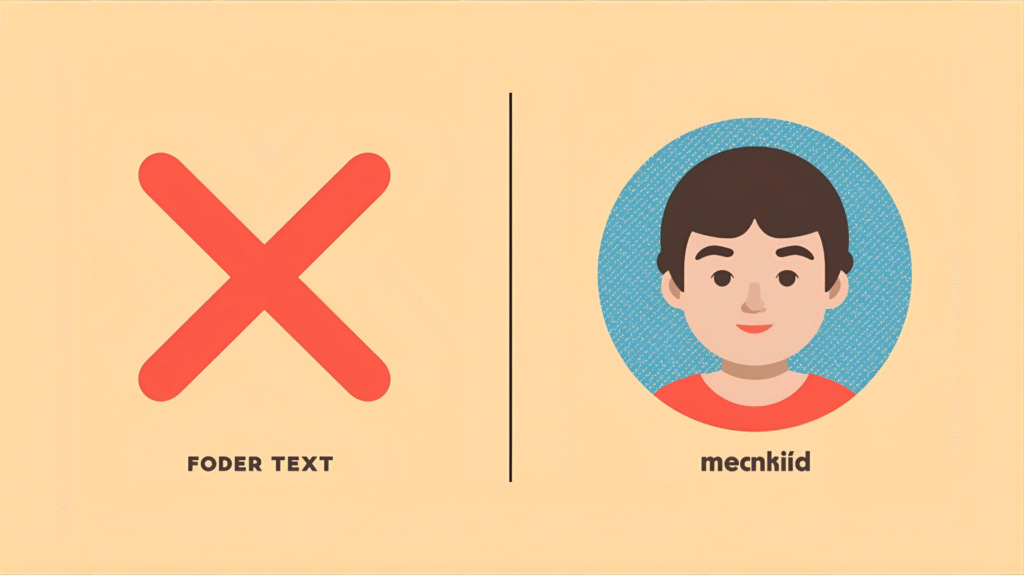
私も新任のころ、通信を「教育実践の記録」として書いていました。
「児童は活動に主体的に取り組み、協同的に課題を解決していた」
こんな書き方です。
でも、保護者からの反応は薄く…😅
あるとき、表現を変えてみました。
「友だちと声をかけ合いながら、“あとちょっと!”とがんばる姿がありました」
すると返事に
「先生の言葉で、子どもの様子が目に浮かびました」
と書かれていたのです。
専門用語より、生活の言葉
これが保護者に届くカギだと気づきました。
【本題】保護者に響く言葉の選び方
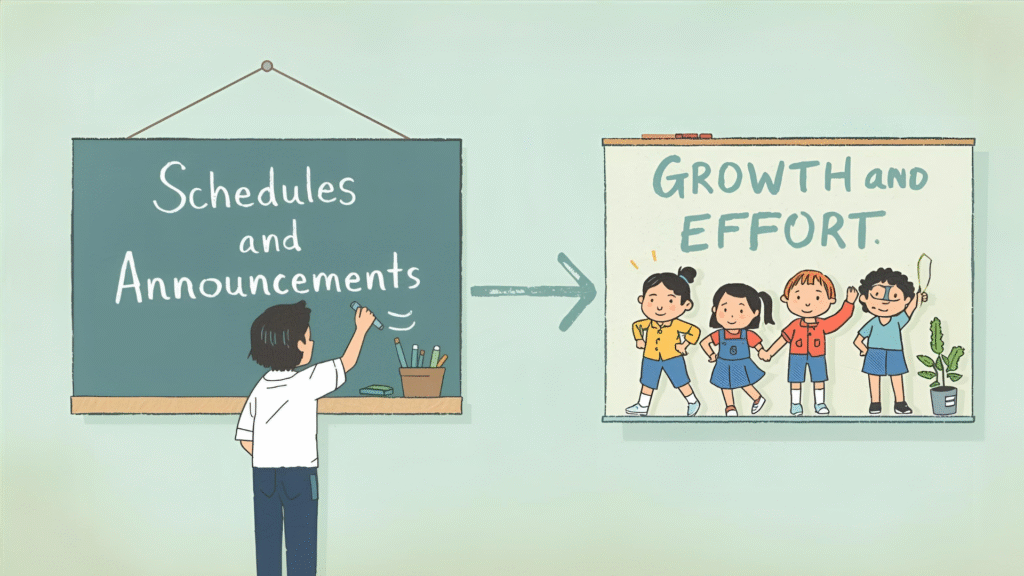
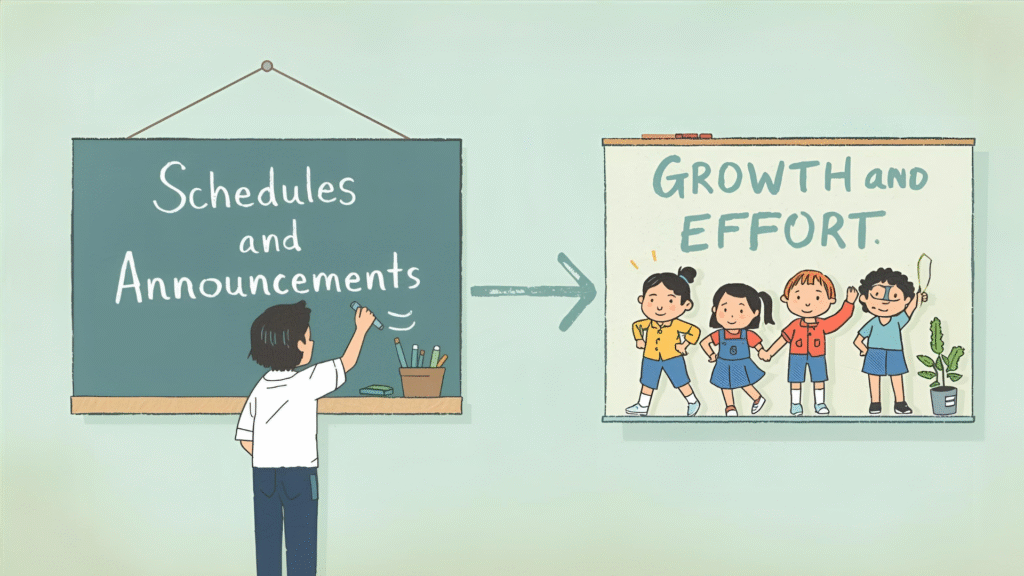
実践報告を“生活の言葉”に変える
NG:「児童は役割を意識し、主体的に活動していた」
OK:「自分の役割を思い出し、“ぼくがやるよ”と声をあげていました」
平易だけど“あたたかい”表現
「すばらしい協同的な姿」ではなく
「見ていて思わず笑顔になったやりとり」
冗長さを避けるコツ
一文一場面に絞る
“そして、また、さらに”を多用しない
感情は「先生の驚き・喜び」を短く添える
短くても伝わる、やわらかい表現が保護者の共感を生む
【実践編】ビフォー・アフターで見る言葉のちがい
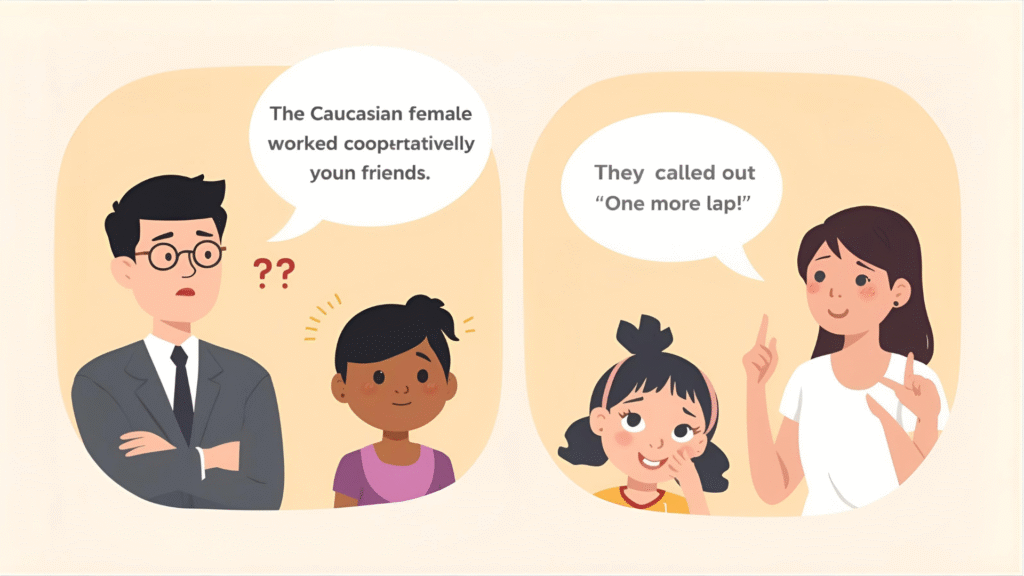
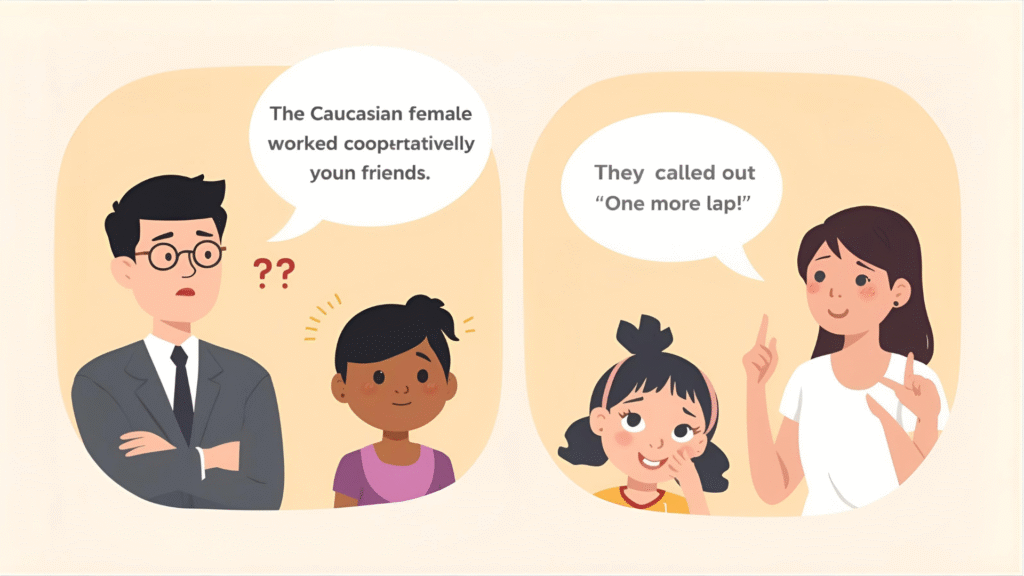
Before:実践報告風
「児童は友人に働きかけながら協同的に活動を行っていた。その中で自分の考えを述べる姿が見られた。」
After:やさしい通信風
「友だちに“こっちがいいんじゃない?”と声をかけ、いっしょに考える姿がありました。」



これなら子どもの声が聞こえてくる感じがします。



難しい言葉より、生活感のある表現が届くんです。
【通信の役割】“教育論文”ではなく“家庭の会話のタネ”
学級通信は教育実践の記録ではなく、家庭の会話のタネです。
「今日こんなことがあったんだって!」──そうやって、家での言葉が広がることに意味があります。
専門的にまとめるのは研究会や論文に。
通信では、わかりやすく、やさしく、生活に近い言葉で十分なのです。
【まとめ】むずかしい言葉はいらない





短くても、やさしい言葉だと心に残ります。



だから私は“伝わる表現”を大切にしています。
学級通信は、予定表でも研究紀要でもありません。
家庭と学校をつなぐ小さな手紙です。
一文をやさしくするだけで、信頼の届き方が変わります。
👉 関連記事へ
子どもの主体性を育てる学級通信の書き方—「書けない・続かない」を越える、毎日発行の現実解—
先生も育つ!日々の通信が論作文の力になる理由
振り返りジャーナルの意義と実践法 ※準備中