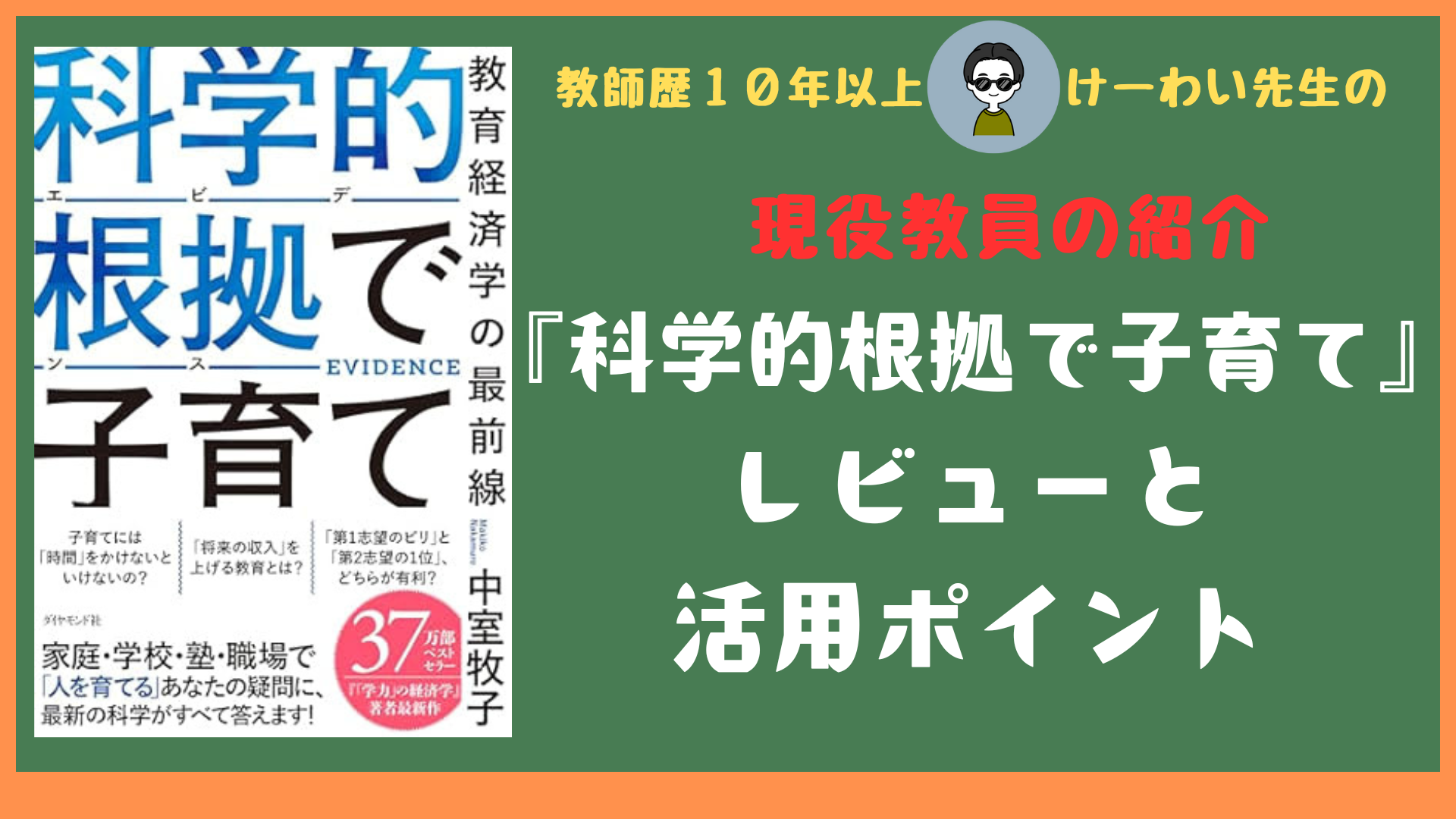「その子育て、根拠はありますか?」
子育てや教育において、感覚や常識では判断しきれないことが増えています。
そんな中で手に取ってほしいのが、『科学的根拠(エビデンス)で子育て』。
この本は、教育経済学という視点から、子育て・教育の「本当に効果があるもの」をデータで示す一冊です。
本記事では、現役教員としての視点を交えながら、本書の要点・おすすめの読み方・家庭や現場での活かし方を解説します。
どんな本?基本情報と注目ポイント
● 著者紹介と本の特徴
著者は、教育経済学者の中室牧子氏。
“教育にお金をかけるなら、どこにどうかけるべきか?”をデータで示すことに特化した研究者です。
この本の特徴は、「なんとなく良さそう」ではなく、明確なエビデンスに基づいて“教育の費用対効果”を読み解く視点が得られること。
 けーわい
けーわいたとえば「早期教育の効果は何歳まで?」「習い事に意味はある?」
といった問いに、データで答えてくれます。
● よくある「子育ての誤解」に一石を投じる切り口
「学力がすべてではない」→でも“学力が高いと収入も高い”のは事実
「子どもには自由を」→でも“時間投資”は早いほうがリターンが高い
「兄弟は同じように育てるべき」→でも“家庭内格差”の影響は大きい
こうした誤解に、データと論理で冷静に向き合えるのが本書の魅力です。
教育現場とのつながりを感じた視点



読みながら何度もうなずきました。
“データが示すこと”と“教室で起きていること”が、
こんなにも一致するなんて。
● 非認知能力に関する部分の共感
本書では、将来の年収や幸福度を左右する“非認知能力”の重要性が繰り返し説かれます。
これは現場でも強く実感するテーマです。
特に印象的だったのは、「家庭環境が非認知能力に与える影響」がデータで示されていたこと。
“時間をかけたかどうか”が子どもの自制心ややり抜く力に直結するという指摘には、大きくうなずかされました。
● 「教員の役割」に通じる視点
「結局、教員の質が最も重要である」――この言葉は本書の結論の一つ。
現場で働く身としても、教員のまなざし・言葉・信念が、子どもの行動や将来像に与える影響の大きさを日々感じています。
家庭や学校でどう活かすか?
● 家庭での“時間投資”の見直しに
「忙しいから」と関わりを減らすより、「短時間でも密な関わりを」
「勉強させる」より「学びを一緒に楽しむ」
本書を読むことで、“今の過ごし方”が10年後の子どもの姿をつくるという視点が得られます。



「つい“習い事を増やす”ことばかり考えていたけれど、“どう関わるか”のほうが大切なんですね。」
● 教育観の「言語化」のヒントに
教育や子育てについて、“なんとなくの価値観”を明文化する手がかりになります。
学校や家庭で「うちはこう考えている」という方針を共有する第一歩として、本書の言葉が使えます。



自分の子育て観、なんとなくはあったけど、
ちゃんと説明できる言葉がなかった。
けど、今なら言えそうです。
まとめ|「悩んだときに立ち返れる」一冊を持とう
『科学的根拠で子育て』は、正解のない子育てや教育の中で、「よりよい選択肢」を探すための道しるべになる本です。
感情や経験も大切。
でも、迷ったときに“根拠に立ち返れる”視点があるだけで、子どもへのまなざしはぶれにくくなります。



子どもの未来を考えるすべての大人に、
一度は手に取ってほしい一冊です。
▶︎ 関連記事: