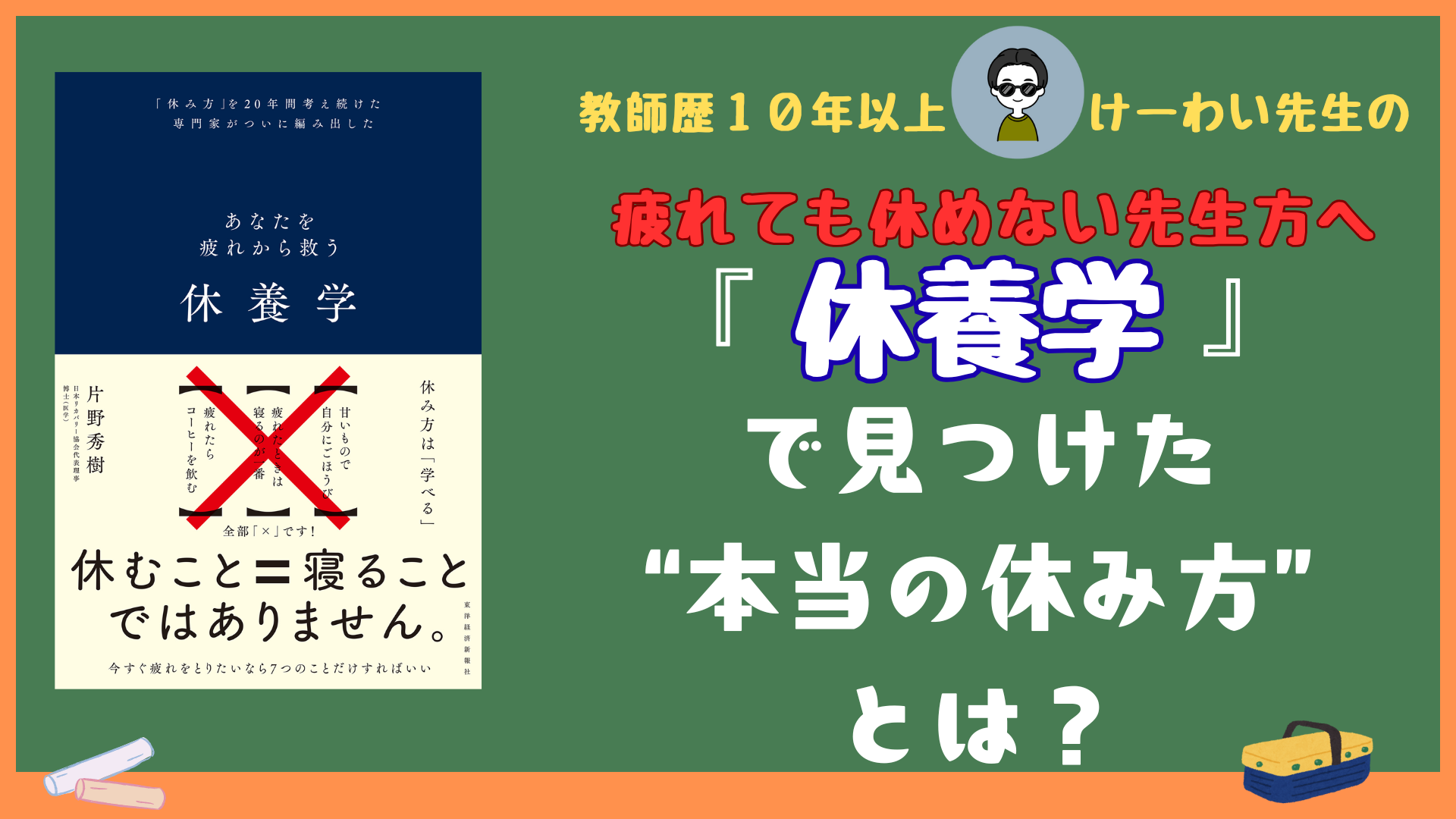けーわい
けーわい「休んでいるはずなのに、疲れが取れない」
そんな感覚に心当たりはありませんか?
仕事が終わっても、気がつけば頭の中は次の授業や保護者対応のことでいっぱい。
寝ても起きても“スッキリしない”状態が続くと、どこかで限界が来てしまいます。
私自身も、運動会や研究授業のあとに体調を崩すことが何度もありました。
「まだ頑張れる」と思っていたけど、それは“本当の休養”ができていなかったから。
この記事では、東洋経済の話題書『休養学』をヒントに、現役教員として気づいた「正しい休み方」についてお伝えします。
頑張りすぎているすべての先生へ、少しでもヒントになりますように。
【なぜ?教員が「休めているのに疲れが取れない」理由】


労働時間だけでは語れない“心と体の疲れ”
実は、「日本の労働時間はOECD平均より少ない」という事実。
それでも約8割の日本人が「疲れている」と感じているのはなぜでしょうか。
その理由は、時間ではなく「質」にあるといわれています。
特に教員は、授業・保護者対応・校務分掌など多岐にわたる仕事を同時進行で抱えています。
さらに、放課後や休日に持ち帰る“見えない業務”が、心と体の回復を阻んでいるのです。
「ちゃんと休んでるのに疲れが取れない」の正体
体は休めていても、心と脳が休めていなければ、真の意味での休養にはなりません。
横になっていても頭が働いている状態では、むしろ疲労は蓄積されていきます。
疲労とは「能力が一時的に下がった状態」であり、放置すると慢性疲労やバーンアウトにつながる危険も。
【体験談|研究授業後に“熱”で気づいた本当の疲れ】





「また熱出したの?大丈夫?」――
家族の一言が、心に刺さりました。
「休めていない」自分を正当化していた。
かつての私は、「疲れているけど、寝ればなんとかなる」「子どもたちのために頑張らなきゃ」と、自分を追い込んでいました。
でも、研究授業や運動会のあとに高熱を出すことが続いたとき、ようやく気づいたのです。
これは、体が出しているSOSなのでは?と。
実は、校長と馬が合わないと感じていた時期には、2週間以上、微熱が続いていたこともありました。
その頃の私は、体調不良を「自分が弱いからだ」と思い込んでいて、誰にも相談できずにいました。
でも、今ならはっきり言えます。あれは弱さではなく、限界のサインだったのだと…。
疲労は仮病じゃない。予兆を見逃すな
疲労は病気ではないからこそ、「気合で乗り切れる」と思われがち。でも、それはとても危険です。
体の小さな不調や気分の落ち込みは、休養のサイン。
無視して走り続ければ、【取り返しのつかない心身の損傷】につながることもあるのです。
疲労は仮病じゃない。予兆を見逃すな
疲労は病気ではないからこそ、「気合で乗り切れる」と思われがち。でも、それはとても危険です。体の小さな不調や気分の落ち込みは、休養のサイン。無視して走り続ければ、【取り返しのつかない心身の損傷】につながることもあるのです。
【休み上手は回復上手!『休養学』が教える新しい休み方】
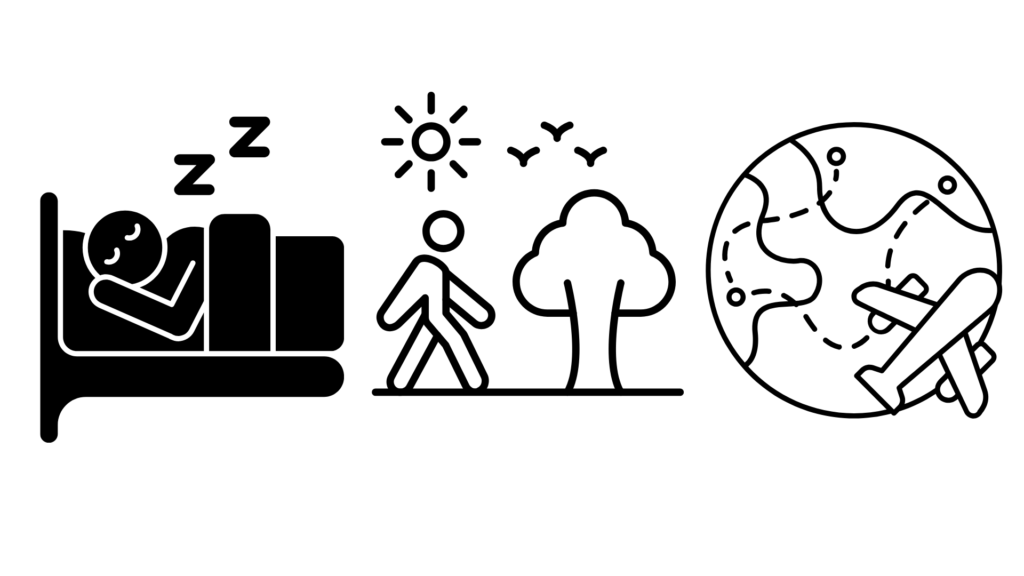
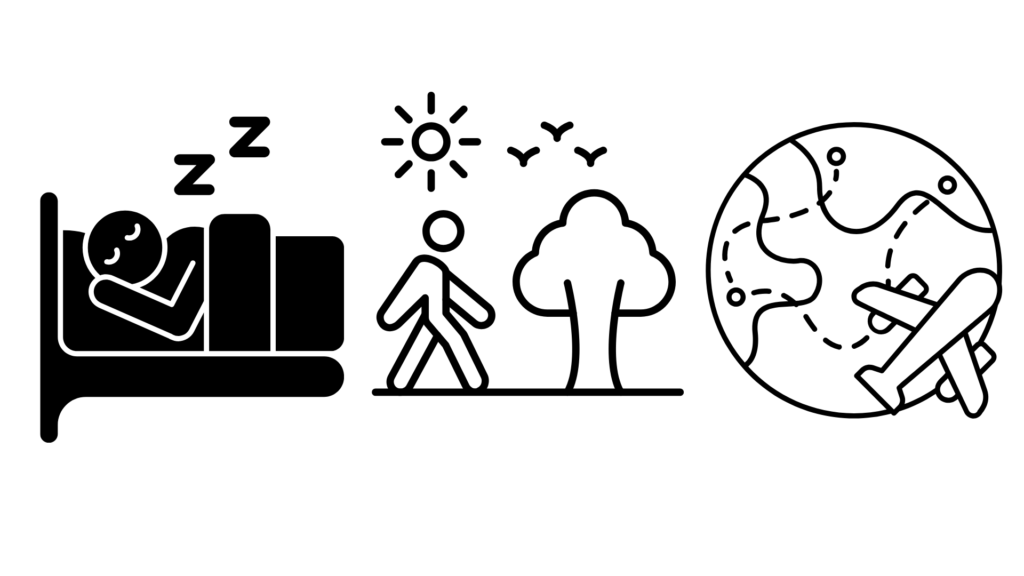
「休養=寝ること」だけじゃない!3つの休養バランス
片野秀樹氏の『休養学』では、休養は以下の3つに分類されています。
生理的休養:睡眠・仮眠・軽い運動・食事管理
心理的休養:家族や友人との時間・趣味・森林浴・創作活動
社会的休養:旅行・模様替え・転職や異動など環境を変えること
これらをバランスよく取り入れることで、初めて“回復する休養”になります。
攻めの休養って何?仕事以外で自分に“いい負荷”をかける
「攻めの休養」とは、ただ横になっているだけの「守りの休養」と相対的な考え方です。
たとえばウォーキングやヨガ、作曲やDIYなど、自分にとって楽しくて負担にならない活動で心と体が“元気を取り戻す”のです。
これはアスリートが実践する「超回復理論」にも通じます。
【今すぐできる!教員の“攻めの休養”アイデア7選】





やる気が出ない日は、家でゴロゴロしがちです。
森林浴や散歩で自然に触れる
ヨガやストレッチで軽く汗を流す
趣味の時間を確保する(絵を描く、楽器を弾くなど)
好きな音楽を流しながら部屋を模様替え
土曜日の午前に来週の計画を立てて心を整える
美味しくて体に優しい食事を意識する
ペットや家族との何気ない会話を楽しむ
これらは、どれも一見“特別なこと”ではありません。
けれど、意識して取り入れることで心身のバランスを取り戻す力になります。
無理をせず、自分にとって心地いい方法を一つずつ見つけていくことが大切です。
小さな工夫で、心と体は確実に変わっていきます。



やる気が出ない日こそ、
少しでも外へ出てみることを試してみても
いいのかもしれません。
【まとめ|“休む勇気”が、教室を救う】


教育現場は常に忙しく、目の前の子どもたちを優先するあまり、自分の健康を後回しにしがちです。
でも、あなたが元気でいることこそ、子どもたちにとっての一番の環境です。
「仕事が一段落してから」ではなく、「まず休む」。それが、今を乗り切る一番の近道かもしれません。
まずは、今週末。ひとつでも「攻めの休養」を取り入れてみませんか?
※あわせて読みたい:関連記事
教員のストレス対策まとめ(https://kyouikunizettaikaihanai.com/teacher-stress-relief-habits/)
教員が夏休みにやるべきこと(https://kyouikunizettaikaihanai.com/summer-tasks-for-teachers/)
教員の健康管理術 (https://kyouikunizettaikaihanai.com/teacher-wellness/)