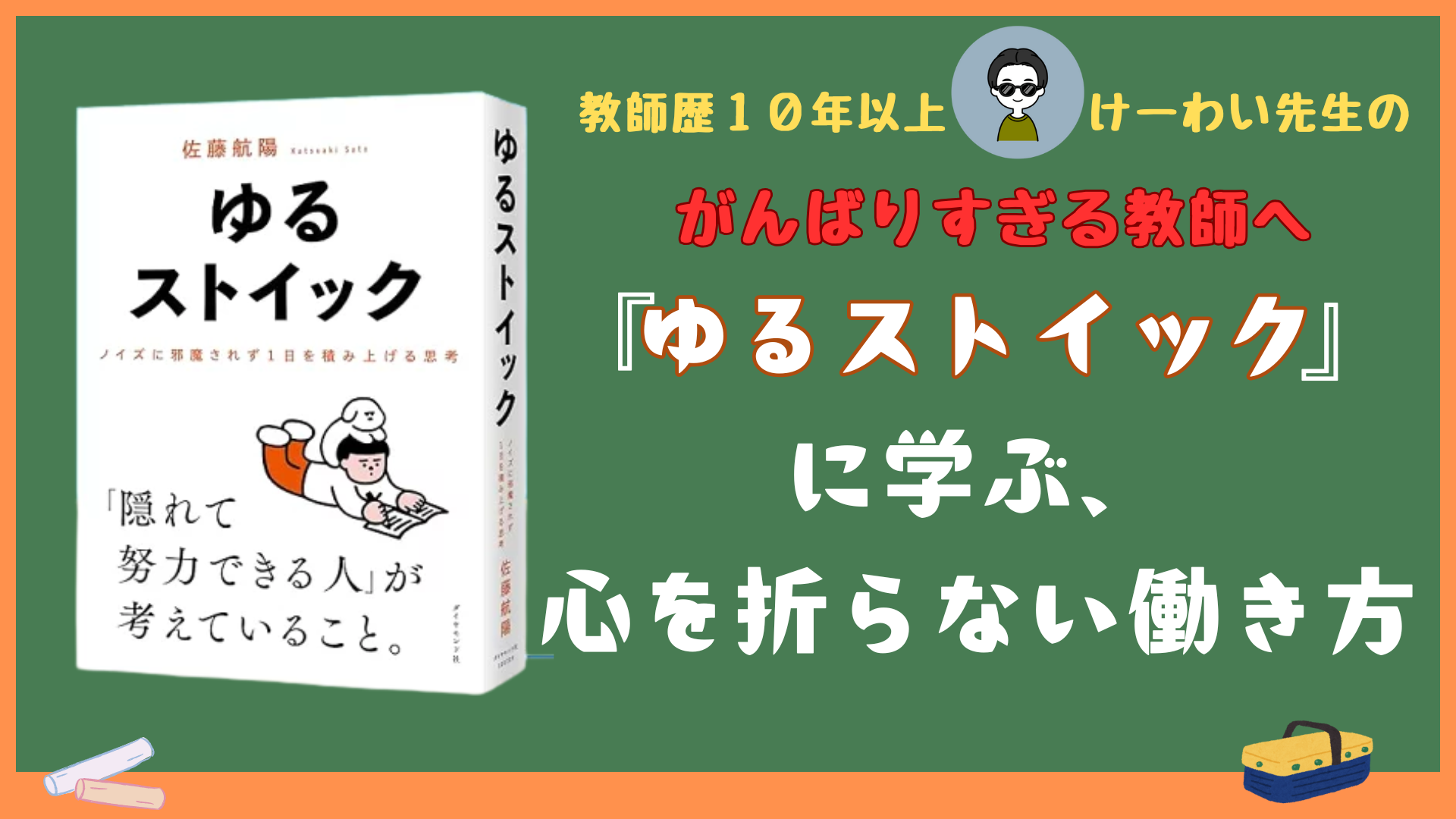導入|【がんばりすぎる教師へ。あなたに「ゆるさ」は足りていますか?】
 新卒先生A
新卒先生A子どもたちのためにって頑張ってきたけど、
最近ちょっと疲れてきたかも…。
教師という仕事は、常に「正しさ」と向き合う職業です。
子どもに、保護者に、同僚に——ときに自分にさえ、正論を突きつけてしまう。
けれど、気づけば心も体もカチカチに。「正しいはずの言葉」が、誰かを傷つけ、自分を追い詰めていた——そんな経験はありませんか?
今回ご紹介するのは、そんな“がんばりすぎる先生”にこそ届けたい一冊、『ゆるストイック』。
「自分を律しながら、他者を許す」この新しい生き方は、ストレスフルな教育現場にこそ必要な視点です。
本記事では、筆者自身の体験とともに、「ゆるストイック」の考え方が教育現場でどう活きるのかを掘り下げていきます。
「頑張らない」の先にある、本当のストイックさ。
あなたも、少し肩の力を抜いて、読み進めてみませんか?
筆者の背景|【理想を語りすぎて、現実がついてこなかった日々】
私はこれまで、「こうあるべき教育」を熱く語ってきました。
指導の場面では一切妥協せず、「正論」で生徒にも同僚にも向き合ってきたつもりです。
けれどある日ふと、自分の中に“ひとりよがりな正しさ”があることに気づきました。
例えば、生徒の態度が気になるとき。
「なぜやらないのか」と叱責する自分の言葉の裏には、「やるべきことはやるべき」という強い信念がありました。
しかしその信念が、相手の背景や心の余裕を見逃していたこともあったのです。
そんな中で出会ったのが、『ゆるストイック』という考え方でした。
自分を律する「ストイックさ」と、他者を許す「ゆるさ」を両立すること。
その言葉に、私はこれまで置き去りにしてきた“人間らしさ”を思い出しました。
教育は正解のない営みです。だからこそ、自分の理想を押しつけるのではなく、「ともに歩む」柔らかさが必要なのかもしれません。
ゆるストイックとは何か?|【「頑張らない」が目的になっていないか】
最近、「頑張らないでいい」「ありのままで」という言葉をよく耳にします。
それ自体は決して悪いことではありません。
過剰な自己犠牲を強いてきた社会の反動として、多くの人が癒しを求めた結果とも言えます。
けれど、『ゆるストイック』はこう問いかけてきました。
「頑張らないこと」が目的になっていないか?と。
本来、「頑張らない」という選択は、目的地へ向かうための戦略であるはず。
それがいつの間にか「現状維持の言い訳」になっていないか、自問する必要があります。
この本が提唱する「ゆるストイック」とは、自分にとって必要な努力を見極め、淡々と積み重ねていく姿勢です。
他人と比べるのではなく、昨日の自分よりほんの少し前に進む。
周囲に厳しさを押しつけるのではなく、他者のペースを尊重する。
それは、ストイックさの再定義でした。
「ガムシャラに頑張る」でも「完全に力を抜く」でもない。
淡々と、自分の信じる歩幅で進む。その先にしか、本当の達成感や成長はないのだと思います。
教育にどう活かす?|【教員としてのゆるストイックな在り方】
では、この「ゆるストイック」の姿勢を教育現場にどう活かせるのでしょうか?
まず大切なのは、余白を持つことです。
生徒との対話においても、同僚とのやりとりにおいても、「すぐに結論を出さない」「言い切らない」勇気を持つ。
また、自分の中にある「正しさ」を疑うことも、ゆるストイックの一歩です。
正論はときに、相手の状況や心情を無視する凶器になります。
自分の理想を声高に叫ぶのではなく、まず相手の声に耳を傾ける。
そこに、共に育ち合う関係性が生まれます。
子どもも教師も、人間です。
完璧な指導よりも、「人としての誠実さ」と「柔らかな在り方」が、心に残る教育をつくるのではないでしょうか。



理想ばかり語っていたあの頃、
自分にも相手にも厳しすぎたかもしれない…。
実践編|【今すぐできる「ゆるストイック」習慣】
①「願望」と「現実」を区別する日記をつける。
私自身、毎日どちらかの時間に日記を綴っています。
朝は「これからの期待」を、夜は「心のもやもや」を言語化することで、頭と心を緩めています。
②一日一回、自分の「手を抜くポイント」を決める。
たとえば、私は国語の教材研究には力を入れますが、算数は教科書ベースで割り切っています。
力のかけ方にメリハリを持たせることで、長く続けられる感覚があります。
③「淡々とやる」を楽しむ技術を身につける。(例:教室掃除や連絡帳記入など)
正直、これが一番難しいと感じます。
たとえ保護者から厳しい声があっても、今できることを淡々とやる。
ある意味、禅の境地のような感覚かもしれません(笑)
淡々と続ける力は、特別な才能ではなく習慣で身につきます。
大切なのは、派手な変化よりも、毎日5ミリずつの進歩を見つけることです。
未来編|【不確実な時代を「ゆるく強く」生きる】



これからの時代、どう立ち振る舞えばいいんだろう…。
生徒も保護者も、価値観がどんどん変わっていく。
正しさを押し通すだけじゃ、もう通用しないのかもしれない——。
現代は、二極化と淘汰の時代です。
競争のプレッシャーが認知能力を下げ、人間関係や働き方の分断を生んでいます。
そんな時代にこそ、柔軟に考える姿勢——つまり「ゆるストイック」が必要です。
「今日が人生最後の日だったら何をする?」と問い続けること。
自分とは遠い存在の気持ちを想像し、寄り添うこと。
そして、論破や優位性に執着するのではなく、自分の人生に集中すること。
それこそが、変化の激しい社会に対応する本当の知性なのだと思います。
まとめ|【ゆるストイックで自分と世界がラクになる】
「折れないけど、曲がれる」——そんな人でありたい。
教育現場は、毎日が判断と選択の連続です。
その中で、自分の軸を保ちつつ、他者を思いやる柔軟さを持つことはとても大切。
『ゆるストイック』の考え方は、ただ“ゆるい”だけでも、“ストイック”なだけでもなく、その中間でバランスをとる知恵です。
無理に頑張り続けるのではなく、頑張り方を見直して、自分らしい歩みを選ぶこと。
他人と比べることなく、昨日より少し前に進む。
そんな小さな積み重ねが、自分の力になり、周りの空気も変えていきます。
まずは今日、「淡々とやる」ことから始めてみませんか?



ちょっとずつでいい。
自分のペースで、でも確かに進んでいけたら——それが一番かも。